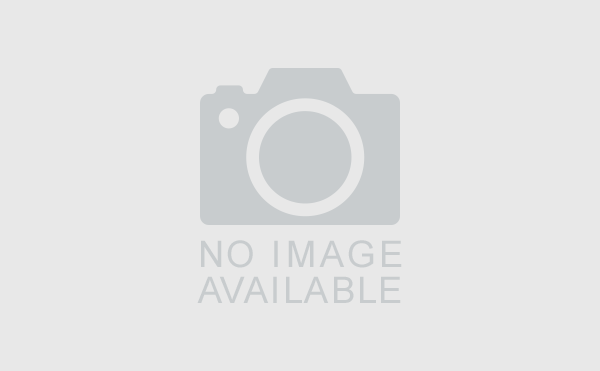古代史雑感 『続日本紀』と「多賀城碑」
はじめに
多賀城と大野朝臣東人に関する史料は、私が不案内で関与できない考古学的なもの除けば、頼れるのは「多賀城碑」と『続日本紀』だけである。史料に制約があるが、『続日本紀』に記載されたことを軸にして考えられる限りで私見を述べてみたい。
本稿は『続日本紀』を読んでいたときに抱いた違和感から始まる。それは二つある。一つには、柵と城は区別する必要があるのではないかということ。二つには、果たして大野朝臣東人は多賀城とのかかわりがあるのか、あるとすればどのようなかかわりかというものである。
一般的には柵、城との間に違いがあるという研究は見られない。しかし全く同じではなく、いくつかの重要な違いがあると思われる。大野東人の東北へのかかわりを考える上でもこれは重要な問題をはらんでいるのではないだろうか。
第一節 柵と城の違い
第一項 柵の時代 ―― 『続日本紀』に書かれた柵
『続日本紀』では、柵と城とを比べると、一般的に柵の名が先行する。和銅二年(709年)七月一日条に出羽柵が初出する。聖武天平九年(737年)には多賀柵、出羽柵の他に、玉造柵、新田柵、牡鹿柵の名前も見える。また、同年九月二十六日には、藤原房前が関や柵を検察とあるなど。多賀についても天平九年四月十一日条に朝廷への藤原朝臣麻呂による言上記事が載る。二月十九日に藤原朝臣麻呂が多賀柵に到着二月二十五日に東人が多賀柵を進発、三月十一日に東人が多賀柵に帰還した、などと。
そして『続日本紀』に城が初めて登場するのは淳仁天平宝字二年(758年)のことであり、桃生城、雄勝城が初出する。したがって、58年より前の時代を「柵の時代」と名付けられるであろう。
第二項 城の時代 ―― 『続日本紀』に書かれた城
淳仁天平宝字二年(758年)の桃生城、雄勝城降は柵戸、城柵などを除き柵の字がほぼ消えていく。逆に城の存在感が際立ってくる。称徳神護景雲元年(767年)十月十五日条には伊治城、光仁宝亀九年(778年)六月二十五日条には覚鱉城(カクベツジョウ)が初出。そしてこの過程の中で、光仁宝亀十一年(780年)三月二十二日条には、有名な伊治公呰麻呂の乱についての記述などでは多賀城と記される。つまり、多賀もすでに柵とは表現されていない。これが『続日本紀』における多賀城の初出であり、724年の多賀「城」碑は『続日本紀』にそぐわないことになるが、ここにはいかなる問題が潜んでいるだろう。このことは第二節で大野東人の多賀城へのかかわりとともに考察することにする。
もちろん「柵」が「城」に変化したのは特に意味があることではないと考える向きもあるかもしれない。例えば、『続紀』の執筆担当者が変わったために用語が変更されただけで、実態は同じだなども考えられる。しかし、私は両者を区別することは有意義なこととして考察してみたい。
柵と城の両者には建築素材、規模、機能などに違いがあるために区別されたのではないだろうか。柵は木偏である。木造であったことを表現しているのではないか。これに対して城は土偏である。固められた土と石で作られていた築地塀に象徴される、より強固な建造物を連想させる。
その理由を考える上で指摘しなければいけないのは「蝦夷と呼ばれた人々(以下、蝦夷とする)」の反乱にヤマト朝廷が苦慮する事態が訪れたことにあるのだろう。そのような状況は、淳仁天平宝字元年(757年)七月八日条で藤原朝臣朝猟が陸奥守に任ぜられたころと時期が偶然にも一致する。朝猟についても第二節で考えることにするが、今の問題は、なぜこの時期に柵より強固と思われる城が必要とされたのかということにある。
この時代の特徴の一つとして言えることは黄金が発掘され、それが朝廷に献納されたことである(注1)。このことがヤマトの東北により深くに侵攻する意欲が高まったのであろう。そのことで蝦夷を強く刺激したのではないだろうか。もともとのヤマトの東北侵攻の動機の一つであった、豊かで広大な土地を有する蝦夷の領域獲得の他に、もう一つの動機が加わったのであろう。その結果、蝦夷の反乱が頻発していく。守備力強化のためには木造の柵ではなく、土と石造りの城に転換していったのではないか。
光仁宝亀十一年(780年)十二月十日には砦という用語もあらわれ、出羽国には大室の塞(せき)もできた。また、桓武天応元年(781年)五月二十七日条には蝦夷が「城や砦を侵略する」とあり、同年九月二十二日条には「奪われた諸々の城塞を回復した」とある。砦や城塞を複数造り蝦夷の攻勢に対応していた様子も伝わってくる。
城を強大化することも必要であっただろう。城には柵戸(一般民と帰順した蝦夷)、住民管理のための政庁施設も必要になる。城自体の防衛的性格も広大かと共に強まったであろう。砦と城の関係は描写されていないが、砦は城への侵攻を防ぐ意味と柵戸の農作業などを蝦夷から守るという意味もあったであろう。城の時代は砦、城塞の時代と呼んでもよさそうである。柵の時代から城、砦、城塞の時代へと移行したきっかけは光仁宝亀十一年(780年)三月二十二日の呰麻呂の乱にあったと言えるだろう。
しかし、光仁天皇の時代、桓武天皇の時代の前半期は征討将軍らによる攻撃失敗、敗戦、逡巡、無策が目立ち、守勢にまわる局面が多かったのである。それだけ蝦夷からの反撃力が強かったとも言えよう。光仁天皇、桓武天皇のいら立ちが「勅」の形で再三再四、表現されているのだが紙幅の都合で、この問題は省略する。
第三項 問題解明の手掛かりとしての岩船柵
柵はまず蝦夷が造ったのではないかという仮説を立てるための史資料は不足している。決め手を欠くことになる。しかし、消極的ではあるが幾分、手掛かりになであろう問題に触れておこう。 『日本書紀』孝徳大化三年(646年)条には、渟足(ヌタリ)柵(新潟市)を設ける、同四年(647年)条には、磐(岩)船(イワフネ)柵(新潟県村上市)を造るとある。
また、『続日本紀』では文武紀二年(698年)十二月二十一日条に石(岩)船柵修理、同四年(700年)二月十九日条には石(岩)船柵造営させたとある。岩船柵造営が『書紀』と『続紀』に重出している。
まず重出の問題である。孝徳紀の柵の記事は、『旧・新唐書』日本伝の「山外は毛人=蝦夷」という言葉に矛盾する。この日本伝の言葉は日本国人・ヤマトの遣使者側の証言を唐が記したものである。「山」が日本アルプスだとすれば越後は「山外」に属する。つまり、ヤマトの支配領域が越後までは及んでいなかったということを意味する。したがって、孝徳の時代にヤマト王権が蝦夷の領域の渟足や岩船に柵を造営することは困難ではないだろうか。孝徳紀の二つの柵の記述は真実を述べたものとは考えられない(注2)。
すると新たな問題が生ずる。孝徳朝の時点で岩船柵造営が行われていなかったとすれば、岩船柵は文武紀のものが初出になる。ところが文武紀では造営が先ではなく、修理が造営に先立っている。この問題はどう考えればよいのだろうか。答えは、すでに岩船柵は建造されていたのではないかということにある。
まず、文武朝が蝦夷征討に向かう。越後の蝦夷がその攻撃・侵攻を防御するために柵を作る。その柵が文武朝に発見され、攻められて奪取される。そしてその柵がより強固な柵へと修理された。そのように見ることもできるのではないだろうか。木製である「木偏の柵」は遺構として残りにくい。岩船柵の遺構がいまだに発見されていないのも、土を固めたり、石材を使用することがなかったからではないだろうか。
歴史の真実は文武時代の出来事を「日本書紀」の孝徳紀が先取りしたのではないのか、という問題に行き着く。孝徳紀の記述は半世紀ほどの繰り上げと考えざるを得ない。
第四項 幾つかの仮説の提示
以上の議論から、柵と城の関係をまとめ、そこから幾つかを仮説を提示したい。
仮説 1. 柵は蝦夷がヤマトの侵攻に対する防御のために築いた防衛施設だったのではな
いか。したがって、多賀柵を始めとした諸々の柵の時代の柵は蝦夷がヤマトの攻撃
からの防衛のために作った施設であった。
2. 城はヤマトの側が蝦夷の築いた柵を発見、占領し、比較的に安定的に支配した段階で築造されたのではないだろうか。築地塀を築き、官衙施設などを備えた段階の名前が城である。
3. 柵という名前だけが記され、城に昇格しなかったものは、上記2.でのような城の修造が行われずに終わった施設ではないか。
4. 城の名しか残されていない施設は、初めからヤマト側が築造したか、柵の段階の記載が省かれたものであろう。
この仮説が成り立つ蓋然性が高いと考えられる理由を述べたい。『書紀』、『続紀』に見えるヌタ
リ柵、イワフネ柵の遺構が現在まで発掘されていないのは、先にも述べた通り、木造の、つまり木
偏の柵で役割を終えたからではないだろうか。
次いで、現在も発掘調査が続く多賀城についてである。当地を訪れたときの違和感であるが、八世紀前半期からあれほど広大な敷地を持つ施設の造営が可能であったのか、またその時点でこの広大な施設が木偏の「柵」と呼ぶにふさわしいものだったのかという問題がある。遺構の案内にも、また一般的な研究書にもその初頭から「多賀城には政庁建物」があった(注3)」という説明されているが、これにも説得力は感じられない。
卑近な例からの考えである。建設ラッシュの昨今、いたる所で古い建物が壊され、地下数階、地上数十階の建物が建てられているのを目にする。このとき古い建物が平屋の民家であったとすれば、その痕跡は新しい深く掘られた広大な新規建造物によって跡形もなく消失してしまうであろう。多賀柵はえぐり取られた基礎工事が浅く、しかも狭い民家に当たる。そして多賀城は深くえぐられた広大な敷地を持つ巨大な新築建造物にあたる。
現在行われている多賀城の発掘作業は新築建造物の痕跡の調査に過ぎないのではないだろうか。決して最初期の木偏の柵であった多賀柵の発掘作業にはなっていないのではないか。
あるいは、こういう場合もあるかもしれない。「多賀城碑」に書かれている「藤原朝臣朝猟修造」に注目すれば、現在の多賀城遺構の発掘調査は、碑が建てられた天平宝字六年(762年)より前のいずれかの年に、按察使鎮守将軍として赴任していた藤原朝猟によって改修された多賀城の遺構であると。
第五項 柵と城 —- 同義とされた理由
柵と城が同義であるという理解が生じた原因について考えてみる。まさか、「柵」も「城」も「き」と読めるから同じと考えられるとする人はいないだろう。これは除く。一つの可能性としては、同じ多賀、桃生、出羽などが柵と城の両方の名で『続日本紀』に記載されていたからであろうか。
さらに『続日本紀』には「城柵」という用語が次に述べる二か所に出てくる。このことも原因になるかもしれない。 城柵が原因であった原因は二つあるように思われる。ヤマト朝廷による東北支配が大きく進展したころに「城柵」の語が見え始める。淳仁天平宝字四年(760年)十月十七日条に「陸奥の城柵を修理するため、東国の人民の力役が徴収される」とある。また弘仁宝亀元年(770年)八月十日条にも城柵の語が見える。柵と城とが一体化して熟語となっていたことに一因があるかもしれない。しかし、「柵」と「城」と「城柵」は区別される必要があるだろう。次のような意味で柵と城は同時存在が可能である。つまり、一定の安定支配が実現したときに、土と石で作られた築地塀に囲まれ、政庁建物を有した城の中にさらに木造の「木偏の柵」を設けて柵戸(各地から集められた一般民や帰順した蝦夷など)として居住した場所と考えることができるだろう。一言で言えば城柵とは、居住施設としての柵を内部施設として持つ城と言えるのではないか。柵、城、城柵は異なった存在である。
二つ目の原因は、城が全盛の時代に城の外側にヤマトの側が造ったと思われる柵が存在していたからである。これ
は、第二項で淳仁宝字二年(757年)あたりからは柵が「ほぼ」消えて、城の時代になったと述べたが、次の二か所は例外であったことに関係がある。柵も城も別途、存在していたのである。
淳仁天平宝字四年(670年)正月四日条で藤原朝猟らが雄勝城を完成させた。その後、朝猟は次の様に天皇に称えられる。「高く険しい峰を越えて桃生柵をつくり、敵の急所である地点を奪った」としかし、この時点ではすでに桃生城がその二年前の淳仁天平宝字二年(758年)十月二十五日条時点で存在していたのである。柵と城が同一のものと考える論者にとっては重出と理解されるかもしれない。だがこれは重出ではない。場所の描写も含めて桃生柵と桃生城とは別物であっただろう。場所も役割も材質も全く異なっていたに違いない。城とは別に柵を作った可能性が大きい。
もう一つ別の柵がその後の時代にもある。光仁宝亀十一年(780年)八月二十三日条には由理柵という名が登場する。秋田城に通じる由理柵は「賊の要害の地に位置している」とある。これは柵戸を住まわせる柵や政庁施設などを内部に備えた城とは別の役割を果たしていた様子がうかがえる。桃生柵と同様に、柵の独自の役割が必要であったのであろう。このように、柵と城は同じものとは言えそうにもない。
第二節 多賀城と東人、そして朝猟
始めにも述べたように、大野朝臣東人についての史資料は『続日本紀』と「多賀城碑」に尽きるようだ。史資料が少ないため解明できない事柄が多いのだが、現時点で語れることだけをあえて語ってみたい。
私は多賀城碑が「江戸時代に造られた偽作」などの説は採らない(注4)。しかし、多賀城が碑文にあるように、多賀城が大野東人によって聖武神亀元年(724年)に建造されたという多賀城碑の碑文には次のような疑問を感じずにはいられない。
まず、第一節でみてきたように『続日本紀』に見る限りでは、聖武神亀元年(724年)の時点に「多賀城」という言葉は存在せず、聖武天平九年(737年)え「多賀柵」と書かれたのが多賀の初出である。したがって、「多賀城神亀元年建造」は『続日本紀』の記述とは合致していない。この点をどうとらえたらよいのだろうか。
第一項 多賀城と東人の接点
大野東人が多賀城を建造したとすれば、『続日本紀』によってその年を絞り込めるかを確認してみよう。
まず、東人が神亀元年(724年)時点に東北と関与したという明確な記載は存在しない。東人が東北に最初に姿を現すのは、聖武天平元年(729年)九月十四日条において陸奥鎮守将軍としてであった。
そして聖武天平九年(737年)では『続日本紀』では多賀「城」ではなく多賀「柵」が初出する。蝦夷によってつくられた最初の柵に改良が加えられたか否かは不明だが、名前は多賀柵であって多賀城になってはいない。
多賀城碑は天平宝字六年(762年)に建てられた。そこには同年(762年)に「東海東山道節度使藤原恵美朝臣朝猟修造」と書かれている。この修造は次の二つのいずれであろう。
1 柵から城へのもの。
2 城から城へのもの。
1の場合である。このときには762年まで多賀には柵しか存在していないことになる。すると、762年まで多賀に城は存在していないことになるので、東人が多賀城に関わることは不可能である。なぜならば、東人は聖武天平十二年(740年)には東北を離れる。藤原朝臣広嗣の乱を平定するために九州に向かうからである。そしてもっと決定的なのは、彼の没年が同十四年(742年)であったからである。
これに対して2の場合には東人がわずかながら多賀城にかかわった可能性は残る。朝猟修造の前の、東人によって建造された古い多賀城があった可能性を探ることになる。その時期は、聖武天平九年(737年)から東人が東北の地を去る聖武天平十二年(740年)までの間であったということになる。多賀城建造と東人とが結び付くチャンスは、あったとしてもこの短い期間以外には残されないことになるだろう。
第二項 東人の功績と多賀城碑
どの時代であれば多賀城碑に東人の名が多賀城建造者として残るのか、その可能性、必然性がある時期はいつなのかのかについても見ておきたい。
多賀城碑に建造年として記された聖武神亀元年(724年)の記事である。海道の蝦夷が反乱。佐伯宿祢児屋麻呂が蝦夷により殺害される。これに伴い、同年四月七日 藤原朝臣宇合が持節将軍、高橋朝臣安麻呂が副将軍として東北へ向かう。同年五月八日 鎮狄将軍小野朝臣牛養が派遣される。出羽国の蝦夷鎮圧。同年十一月三日 宇合、牛要ら帰京。ここまで、東人は東北に登場していないが、多賀城碑では「神亀元年(724年)に東人が多賀城建造」。明らかに、『続日本紀』と多賀城碑とでは食い違いを見せている。彼が多賀城碑に名を残すような活躍の場も描かれていない。
ところがそれにもかかわらず、東人が対蝦夷戦で活躍したのではないかという説もある。『続日本紀』には次のように書かれていた。神亀二年(725年)一月二十九日、「従五位上東人十四位下」に進階と。つまり東人は「従五位下→従五以上→正五位下→正五位上と三階もの昇進をしている。このことは議論の余地を残す。なぜ三階も。
Wikipedia によると、多賀城を中心とした蝦夷征討戦において「副将軍的な役割を果たしていたのではないか」とされている。
しかし『続日本紀』には多賀城の築造記事さえ存在しない。さらに奇妙なのは、724年には藤原宇合が持節将軍として、また高橋朝臣安麻呂が副将軍として東北経営の責任者として存在していた。彼らを差し置いて、なぜ「多賀城築造」が東人の業績とされたのだろうか。宇合、安麻呂の立場、面子やいかにという問題になる。724年に東人が多賀城に関与したということは無さそうである。
東人が東北に最初に姿を現したのは『続日本紀』では聖武天平元年(729年)九月十四日条において陸奥鎮守将軍としてであった。このとき、東人はその役割にふさわしい言上を行っている。
「鎮守府の兵士と人民らのうち、勤務ぶりや軍功を記録してもよい程の者には、冠位を授けて後輩たちのはげみにさせたいと思います。」これに天皇が同意し具体的な褒章を行うよう東人に「勅」が送られている。
さらにその後、東人は決定的に重要な役割を果たす。それは同九年(737年)一月二十三日の言上とその後の実績にある。東人は陸奥国から出羽国まで尾勝を経ない直通路を造る必要性を言上し、朝廷から承認される。
それを受けて朝廷から持節大使藤原麻呂が陸奥国に派遣される。東人は麻呂と協議の上、直通路を完成させるのだが、このときに麻呂は東人の将軍としての有能さに触れて感嘆し、朝廷にその旨を報告する。麻呂の言上である。「臣下の麻呂は愚かで事情に明るくありませんが、東人は久しく将軍として辺要の地にあり、作戦が適中しなかったことは殆どありません。」久しくというのは、おそらく聖武天平元年(729年)に陸奥鎮守将軍として東北に赴任した時点以降を示すのであろう。
ヤマト側からすれば、征夷戦に携わった将軍の中でも東人は、坂上田村麻呂に次ぐ出色の存在だとみなすことができる。この時代に東人が多賀城を築造すればその功績が多賀城に記される可能性はあるだろう。藤原麻呂は637年に流行り病で没するので、多賀城碑の建立などは知る由もないのだが、仮に麻呂の存命中に碑が建てられたとしても、麻呂は多賀城建造者としての栄誉が東人に与えられることに納得することであろう。そして、東人が多賀城を造ったとすれば、やはり737年から彼が九州に向かった740年までであろう。
第三項 多賀城と朝猟の接点
したがって東人は多賀城建造には、きわどい形でかかわっていたという可能性も残っている。しかし、逆に関わってはいなかったという可能性も残されてしまうのである。かかわっていないという後者の場合には、先の1の可能性が生き返ることになる。すると、多賀柵を多賀城に修造した朝猟のかかわりが俄然、注目されることになる。
この場合には多賀柵から多賀城への修造、改修であるから、「城」としての多賀城は新たに建造されたに等しいことになる。すると、これまでの朝猟像は多賀城碑の建立者として注目されてきたが、多賀城建造者としての朝猟という位置にいたことにもなる。そして、このとき朝猟によって建造された多賀城を焼失多賀城」と名付けておこう。というのも、この多賀城は光仁宝亀十一年(780年)に起こった呰麻呂の乱の際に火がつけられ焼失したからである。
『続日本紀』には、その後、多賀城が再建されたという記録は残されていない。しかし多賀の地は陸奥国の中心地、拠点としての位置にあった。したがって新しい多賀城が再建されたはずである。これを「再建多賀城」と名付ける。
現在も行われている多賀城の発掘調査は、おそらく焼失多賀城と再建多賀城の広大な領域をカバーしているのではないだろうか。
最後に —― 本稿を振り返って
史料の不足により断定できない部分は多々残る。
『続日本紀』に記されたことがすべて正しいとは必ずしも言えるわけではないが、本コラムは多くの点で『続日本紀』の記述が正しいものと仮定して議論した。
一つには、天平宝字元年(757年)までは、いっさい城の名は登場しなかった。この時代を私は「柵の時代」と名付けた。ところが翌天平宝字二年に記された桃生城、雄勝城を皮切りにほぼ「城の時代」に移っていく。このことに意味があるというのが私の議論の基本にある。
二つには、柵と城とではその建築素材、規模、機能に違いがあるのではないのか、という点に注目して議論を進めた。特に、柵は木偏であることから分かるように木材を建築材料にしていたであろう。そのことによって当然、戦闘行為における強度や規模、役割なども制限を受ける。よって、「柵の時代」は次第に終焉を迎えることになる。『続日本紀』はその違いを正直に表現していたのではないだろうか。砦、城塞の語の出現も「城の時代」に一致している。蝦夷との戦闘が激しくなったなどが考えられる。
三つには、『続日本紀』の記述によると、大野東人がいつから多賀を含む東北地方で活動を始めたのか、さらに彼が多賀城を建造したとすると、どの年代ならばそれが可能かを論じてみた。東人が多賀城建造にかかわったのか、かかわらなかったのか、二つの可能性はともに残されることになった。もし東人が多賀城建造にかかわっていないとすれば、誰が多賀城を建造したのかという問題が残された。
さらに、『続日本紀』には多賀城とのかかわりについての記述がない藤原朝猟だが、「多賀城碑」のわずかな碑文から朝猟と多賀城とのかかわりについても議論を試みた。東人が多賀城建造に関にわっていないとすれば、朝猟による多賀城修造の意味は大きくなっていくのではないだろうか。多賀柵が多賀城に修造されたとも考えられるからである。
(注1)黄金については重出の問題がある。孝謙天平勝宝元年(749年)二月二十二日条と称徳天平神護二年(766年)六月二十八日条に「陸奥国で我が国初の黄金が出土」という記事がある。ここには重出があることになるが、どちらにしても八世紀中ごろに黄金が発掘されて、その価値を朝廷が認識し始めたということは間違えのないことである。
(注2)拙稿「斉明紀から見える『日本書紀』の虚構 蝦夷征討記事について」(東京古田会ニュースNo.214))で述べたことである。『続日本紀』元明紀の和銅二年(709年)条では、「征越後蝦夷将軍」が任命されていた。その意味することは、孝徳朝の六十年後の元明朝ですら越後が対蝦夷戦の最前線であったことを示しているのである。孝徳天皇の時代にヤマト側が越後に柵を造ることは不可能であろう。
(注3)例えば、考古学研究による『太宰府と多賀城』岩波書店 石松好雄・桑原茂郎著 92頁
(注4)例えそれが偽作だとしても、ではなぜ江戸時代にそのような偽作が行われれたのかは歴史として解明されるべき課題になるであろうが、今回そこには立ち入らない。