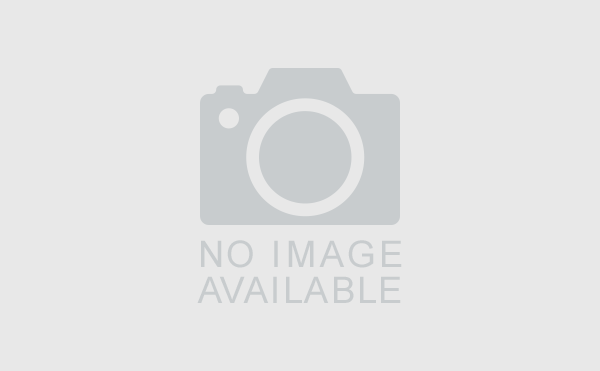神功皇后紀に隠された西暦年
はじめに
本稿は十數年ほど前だったかに書いたものに、若干の手直しを加えたものである。
『日本書紀』に対して、また「一般的にそう見なされている常識的古代史」に対して疑いの目を向け始めたのが、特に
対中国外交史であった。そして、これは実際の外交の歴史ではないという私の思いが決定的になったのが、神功皇后紀における対中国遣使記事であった。
すでに、拙稿でヤマトの王権が初めて中国と国交行ったのは遅く、咸享元年(670年)であったと述べた通り、咸享
元年以前の対中国国交の『日本書紀』に書かれた記事はすべて虚偽報告ということが私の基本的見解である(注1)。ま
た、『書紀』には書かれていないが、倭の五王に関する常識的解釈も史実からは程遠い理解だということも、続編で述べ
てみたいと考えている。
最初は神功皇后紀の中国との国交記事である。神功皇后紀の遣使記事を史実だと考える歴史家は皆無に近いだろ
うが、虚偽報告がなされる際の『日本書紀』などの手法を知るために、神功皇后紀の対中国遣使関係から検討していく。
よく指摘されるように、神功皇后紀は神功皇后一人を卑弥呼と壹(臺)与の二人に見立てていた。結論から言えばこれは比定とか、神宮皇后の資料が、実際にあったものを紛失したなどために『魏志』、『西晋書』から引用して補ったとか、借用したなどではなく、むしろそもそも無かった遣使関係を『魏志』などから盗用、剽窃したというべきとも考えられる。よって、その理由を私なりに推理し、抉り出してみたい。『日本書紀』の手法を見極め、特に外交史における手練手管に載せられないようにしたい。
第一項 神功皇后紀の遣使記事
以下、日本書紀・神功紀の引用である(注2)。
ア. 神功皇后 39年 この年の太歳己未―――魏志倭人伝によると、明帝の景初三年六月に、倭の女王は大夫難斗米を遣わして帯方郡に至り、洛陽の天子にお目にかかりたいと言って貢をもってきた。太守の鄧夏は役人を付き添わせて、洛陽に行かせた。
【景初三年は西暦で239年】
イ. 神功皇后 40年―――魏志にいう。正始元年、建忠校尉梯擕らを遣わして詔書や印綬をもたせ、倭国に行かせた。
【正始元年は西暦で240年】
ウ. 神功皇后 43年―――魏志にいう。正史四年、倭王はまた使者の大夫伊声者や耶ら、八人を遣わして献上品を届けた。
【正始四年は西暦で243年】
エ. 神功皇后 66年―――この年は普の武帝の泰初二年である。普の国の天子の言行などを記した起居注に、武帝の太初十月、倭の女王が何度も通訳を重ねて、貢献したと記している。 【泰初二年は西暦で266年】
ところで『書紀』は『魏志』における倭国と魏との遣使関係をすべて引用したわけではない。参考のために『魏志倭人伝』おける卑弥呼・壹与の遣使関係のすべてを挙げておく。、神功紀はこの中のすべてを記録しているわけではなく、次の四角で囲った4つのみを採用している。なぜかは不明である。
景初三年・239 六月 倭の女王が大夫の難升米らを派遣して帯方郡に詣でて朝貢することを求めた
正始元年・240 帯方郡太守の弓尊は建中校尉の悌雋らを派遣し、詔書、印綬を奉じて倭国を訪れ、倭王は使者に上表文を渡して、詔勅に対する謝恩の答礼を上表した
正始四年・243 倭王は再び大夫の伊聲耆、や邪狗ら八人を遣使とし
正始六年・245 詔を以て倭の難升米に黄幢を賜り
正始八年・247 卑弥呼と卑彌弓呼、張政らを派遣
年代不明 卑弥呼以て死し、大作冢(正しい訳「大いに塚を作る;誤訳「大きな塚を作る」。これが定説ではよく採用されている).卑弥呼の宗女壹與立つ
泰初二年・266 西晋書起居注 壹与が遣使
第二項 作為された神功皇后の遣使記事
以上の神功皇后紀にはそれ自身で重大な問題を抱えていた。つまり、第一に、神功皇后紀で『書記』は、「魏志にい
う」、「晋の起居注記す」などのように引用している。その一部だけであるが。
もちろんある国の歴史書で他国の出来事を紹介し、引用するのならありうるだろう。しかし神功皇后紀は、自国の史書で自国の皇后のことを語っているにも関わらず、他国、中国の史書から引用しているのである。しかも、神宮皇后紀の中国との外交記事のすべてが引用で、引用したこと分かるように書いている。正直と言えば正直だが、このような史書が他にあるのかと思い意識していたところ引用したと明示はされてない引用が存在した。それは、白村江戦を記述した『百済本紀』倭人伝である(注3)。
義慈王竜朔二年七月条 「劉仁軌及別帥杜爽扶余隆 帥水軍及粮船 自熊津江往白江 以会陸軍同趨周留城
遭倭人白江口 四戦皆克・・・」
しかしこれを書いた真の主体は誰であろうか。百濟であろうか。「四戦皆克(よんせんみなかつ)」で分かるように、勝利した側、つまり唐からの視線であることが分かる。新羅伝や高句麗伝に記載された文章であれば、突き放して客観的に記述されることもあるだろう。しかし、この文は百濟と倭国との共闘であって、ともに敗戦側であった戦いの記事である。その立場からすれば、百済や倭は「四戦皆負」などのように書かなければならない。
予想通り、この文は一部の語句は異なるが、ほとんどが引用文であり、その種本は『旧唐書』の百済国伝そして劉仁軌伝であった。おそらく百済には白村江戦の資料が残っていなかったのであろう。戦乱の中で資料を残すことができない、あるいは残したとしてもその資料を紛失する、消失するなどがあれば、それらに代わる何らかの資料を求めたくもなるであろう。もちろんこの時期に『旧唐書』は書かれていないが、唐側の資料を手に入れることやその他の情報ルートはあったであろう。
しかし神功皇后紀はその類ではない。もとより、私には咸享元年以前のヤマト王権の対中国国交は無かったという確信があるので神功皇后が魏晋朝との国交関係があったとは考えていない。
第三項 神功皇后紀の執筆者は西暦を知っていた
神功皇后期には次のような重要な点での作為の跡が見える。神功皇后の年号である。管見に入らずかもしれないが、
私が見た限りでは、どの歴史研究者も神功皇后紀の年号の「作為」について論じていないようである。気が付いていない
はずはないと思うのだが。つまり、先の引用には「参考」として西暦年も書いておいた。ア・イ・ウ・エを見てみよう。
ア.卑弥呼が初めて魏に使いを送ったのが景初三年、西暦でいうと239年であるが、上の引用のアで、神功皇后が魏に使いを送ったのが神功皇后紀の39年。
イ.魏から卑弥呼に遣使が送られるのは正始元年、西暦で240年、イで魏から神功皇后に遣使が送られるのが神功皇后紀40年。
ウ.卑弥呼が再び魏に遣使を送るのが正始四年、西暦で243年、ウで魏に神功皇后が遣使するのが神功皇后紀43年、
エ.さらに、壹(臺)与が晋に遣使したのが泰初弐年は西暦の266年、エで神功皇后が遣使したのが神功皇后の66年である。
つまり神功紀の紀年では、西暦から百の位の2を取り去り、下二桁を合わせるという作為が行われているのである。しかも、西暦239年は「太歳己未(つちのとひつじ)」というように、ご丁寧に干支と西暦も合わせている。
ということは、書記の筆者は西暦の存在を知っていて神功紀を書いたことになる。これはほぼ確実なことであろう。では、次の問題であるが、書記の執筆者は西暦をどうやって知ることになったのだろう。私は上記のア、イ、ウ、エの神功紀年は偽作だと考えているが、仮に偽作ではないとしても古代に西暦を知っているというのは情報通を通り越しているように思われる。
西暦は、Wikipediaによると、525年に造られたという。しかし西暦は、731年に『イングランド教会史』が執筆されて以降、徐々に広まっていったにすぎず、教会の中で広く使われ始めたのは十世紀以降であり、さらに一般の人が使い始めたのがキリスト教文化圏であるヨーロッパでさえ16世紀からだと言われている。
すると、まず確実なことは神功紀が書かれたのは525年以降であり、書記の完成した720年以前ということになる。ところが、Wikipediaによると西暦が世界に広まり始めるのは、早くても731年以後ということである。いかにして720年に完成した書記の執筆者は西暦を知り得たのか。私にとっての難問である。いや、難問であった。
この難問を解く鍵は、景教(キリスト教の一流派であるネストリウス派)の広まりにある。中国には唐の初期の635年にペルシャ経由で伝えられたと言われている。当然、日本にも、流行したか否かにかかわらず、景教が伝わったことが考えられる。さほど流行らなかったようであるが。西暦は中国からの渡来人によるものなど、様々な可能性がある。すると、中国でも日本でも、創始者であるキリストの人物像、思想などについても語られ、その中にはキリストの誕生とその年代なども含まれていたであろう。キリストが「厩で生まれた」➡「ウマヤドノミコ(=聖徳太子)」というネーミングも景教を含むキリスト教文化の伝来に伴う発想から名づけられたのかもしれない。
また、景教の影響ではなくとも、シルクロードを通しての中国と中東地域の間で文物の行き来や情報のやり取りがあったわけで、キリストをめぐる様々な情報も入手は可能であっただろう。
したがってもちろん、神功皇后紀は同時代史として執筆されていたわけではなく後代の作であることになる。
第四項 ヤマト王権内の秘密の会話
神功皇后紀の執筆者たちの会話を想像してみよう。
A 「こんな年号があるぞ。これを利用できないかな。」
B 「そうだな、どうせこんな年号(西暦)なんか我々の中でもごく一部の人間にしか知られ
ていないのだから、利用しようと思えばいくらでもできるだろう。で、どうすればいいんだ。」
A 「神功皇后紀のこの記事なんかどうせ架空なのだから、年号も最初の2百の2を取り去って、下2桁にしたらどうだ。それらしくできるんじゃないか。」
C 「だけど、西晋の壹与の記事まで入れると、皇后の生存年が長くなりすぎるぞ。在位だけで
66年になる。寿命がとんでもなく長くなりすぎるぞ。」
A 「ハハハ、そうだな。でも、もっと長生きした天皇もいるじゃないか。神武天皇は在位年数だ
けで76年だぞ。それよりは少ない、問題ないよ。」
D 「266年の後にも倭国の遣使記事があったら、神功皇后をもっと長生きさせなければいけ
なかったかもな。」
B 「そうだな。66年の遣使記事の直後に皇后が亡くなるのもちょっと不自然だから、没年は
69年までにしておこう。」
最後に
神功皇后紀では、個々の記述は明らかに『魏志』や『西晋書』に記載された事象を引用し、さらに神功年号は西暦に変換され、その下二桁を神功皇后の年号とするという作為が行われていた。神功紀における対中国の国交記事は、『魏志』、『西晋書』がなければ描写できなかったに等しいというのが『日本書記』神功皇后紀である。
では、なぜこのような作為が行われたのか。『日本書紀』はヤマト朝廷の由緒書きでありその権威・権力の正当性を述べたものであろう。万世一系と列島早期一元的支配の政治路線を確立するだけでなく、後代にも受け継がせる政治的教育書、指導書であると考えられる。つまり、『書紀』の書かれた時代は唐との国交全盛の時代でもある。様々な「雑音」も入ってくることだろう。「倭国と日本国との関係はどうなっているのか」などの質問も官人などから出されるかもしれない。そして神功皇后紀は、「卑弥呼などという名は天皇家の中にはいないではないか」という疑問に対して答えるために用意されたのであろう。「神功皇后が卑弥呼だ」とするのが模範解答であったかもしれない。
以上で神功皇后期の問題は終えるが、推古紀や舒明紀などの遣使記事についても、ヤマト朝廷の政治路線を守るための何等かの作為が行われているという視点で論じることになる。この点は続編にゆだねたい。
(注1) 拙稿:「近畿ヤマト王権による初の中国遣使は咸享元年である」東京古田会ニュース
No.217号
(注2) 『日本書紀』は、宇治谷孟訳、講談社学術文庫版からのものを参考にした。
(注3) 詳細は拙稿:「新羅史・百済史の史料価値」、東京古田会ニュースNo.213号