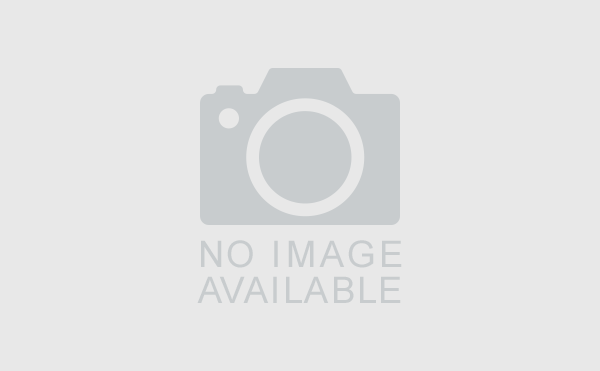古代史コラムNo・4 「王者」対「覇者」
小学生のころ何回か神宮球場に六大学野球の試合を見に行き、父親が慶応大学出身ということで慶応の応援をしていた。応援歌は「陸の王者慶応」。1927年にできた歌だという。今でもその一番は空で歌える。
時は流れる。高校のときにサッカーをやり、大学サッカーの試合をよく見に行った。早稲田の釜本邦茂が活躍する時代。自然と早稲田のサッカーを応援するようになった。その後、ラグビーにも興味を持つようになる。スクラムの押し合いで主導権を握る明治や慶応のスタイルではなく、バックスからパスとランでダイナミックにトライを奪う、早稲田のいわゆる「展開ラグビー」のとりこになった。藤原優の走りなどを思い出す。早稲田の応援歌の歌詞はよく覚えなかったが、その最後で歌われる「覇者、覇者、早稲田」だけは耳に残った。1931年作の曲だという。慶応の応援歌に遅れること四年。
父は野球には思い入れがあったが、サッカーやラグビーには興味がなかったため、慶応が勝とうが早稲田が勝とうがあまり気にしていなかった。また、私も子供のときからの「縁で」野球は慶応を応援していたため、親子で早慶戦・慶早戦ということにはならずに済んだ。もちろんその頃、私は「王者」と「覇者」の違いなどにまったく関心はなかった。どちらも偉そうで強そうだぐらいの印象であっただろうか。
時代はさらにさらに進んで、つい最近のことである。中国の歴史を通史的に把握しておきたいと思い立つ。『史記』、『漢書』などを読む。中国の最古の王朝は夏・殷・周だと習っていたが、しかし夏は文献的資料によっても、考古学的な発掘調査でもその存在は確認できていないため、夏王朝の存在は中国でも認められていない。孔子は自分が理想とする周王朝の先行王朝として夏や殷王朝を重視したため、儒教を信奉する司馬遷の『史記』は夏王朝から始まっている。このため私もそうだったが、夏を実在したものという考えは現在でも一般的には、残っているようだ。
自分の頭の中を整理するために簡単に中国のこのあたりの流れを見る。現在の段階では、文字資料でも考古的資料でも殷が最古の王朝ということになる。次いでBC1046年から周の時代が始まる。周の全盛の時代は西周とも呼ばれ、首都は現在の陝西(せんせい)省西安(後の長安)の近く、鎬京(こうけい)に置かれたと言われる。西周の力が衰退するとともに異民族に追われて、東の洛邑(後の洛陽)に東遷する。これが東周と呼ばれるが、西周の時代に比べて弱体化したものになる。そして、この時代が春秋時代の始まりともされる。BC770年あたりのこととされている。
春秋時代と戦国時代は両方ともに「戦国時代」と呼べるような戦乱の時代という印象だが、両者を分かつもの、それは春秋時代には弱体化したとはいえ東周を王として尊重し、その他の列強の諸侯が「尊王攘夷」の立場を貫き、自らを覇者と位置づけ王者とは名乗らなかった。通常「五覇」と呼ばれている。五覇が誰をさすかは定まっていない。斉・晋の二覇はほぼ確定しているようだが、残りの三覇には諸説あり楚・宋・呉・越・秦のいずれかの国の諸侯ということになるようだ。これに対して、戦国時代は各列強の諸侯がそれぞれ王を名乗り覇権を争う時代である。最終的に勝利するのが秦であった。
今回の慶応と早稲田の応援歌についての話題に目を転ずる。これと関わるのは中国の春秋時代である。つまり、その時代の王者と覇者の位置関係に注目すると、春秋時代には名目上では王者が覇者の上位にあったということになる。そして、まず先に応援歌を作り「王者」を名乗ったのは慶応である。これに対して後発の早稲田の応援歌は、自ら中国の春秋時代には王者の下位に位置付けられる「覇者」を歌詞に選んだ。早稲田応援歌の作詞者は中国古代史の事情を知らなかったのであろうか。もちろん、春秋時代の政治・軍事の力関係などは大学の応援歌の歌詞とは無関係だということで済ますことはできる。しかし、これを知ってしまうと私は何やら気になってしまった。
あるいは、早稲田の応援歌の作詞者が春秋時代の王者と覇者の位置関係を知った上で、あえて覇者を選んだと考えてみよう。春秋の時代には王者が奉られていたが、戦国時代には逆に覇者だった秦が王者だった周を押しのけて勝者になっていく。つまり覇者は王者に勝つ。「逆転劇が起こるのだよ」、と言いたかったのであろうか。そのような雑念を浮かべながら中国の古典を読んでいた。
両大学の応援歌が試合にどれだけ影響を及ぼしたのかは分からない。様々な競技で勝った負けたを繰り返して来たであろう。
とはいえ、両校の応援歌ができたてからまだ百年足らずしか経っていない。これに対して、中国で王者と覇者が並存していた東周時代、つまり春秋時代は三世紀半以上続いた。この時代の半ばに孔子が生き、東周の不甲斐なさを嘆く時代があった。そしてその後、覇者が王者を名乗り王者が他の王者と戦うBC403年からの戦国時代が続く。そして一人の王者が諸王者を征討する、つまり王者の中の王者が誕生する。それが中国全土を統一し、初の皇帝を名乗った秦の始皇帝であった。BC221年のことである。戦国時代は二世紀近くも続いたことになる。以後、中国では皇帝が入れ替わることがあったとしても、諸王は皇帝にかしずく地位に位置付けられていく。始皇帝以後、王者対覇者の時代は終わりを告げた。
人を殺しあう戦争の時代は一刻も早く終えてほしいものである。一方の六大学の王者と覇者の争い。スポーツの争いは長く続いてもらいたいのだが、こちらは何世紀も続くのだろうか。