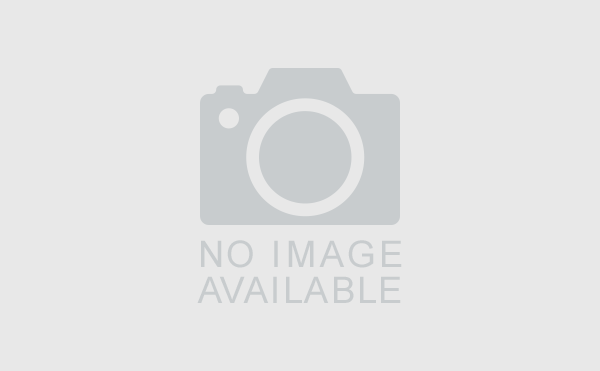「夷狄」考:『論語』と『史記』より
はじめに
『論語』を改めて読んでしばらく考え込んだ。異民族・異文化の民を表す「夷狄戎蛮」などの解説の多くに違和感を覚えたからだ。『論語』には「夷狄」が二か所、「九夷」と「蛮貊之邦」が各一か所で記されている。しめて四か所。
A・「八佾篇」: 子曰 夷狄乃有君 不如諸夏之亡也
夷狄で君主がいることは、中国で(君主の)いないようなことよりよい。(古注による)
B・「子路篇」: 樊遅問仁 子曰 居処恭 執事敬 与人忠 雖之夷狄 不可棄也
樊遅が仁について尋ねた。孔子が言った。家にいるときはくつろぎ、礼事を執るときは敬ましく、
人と交際するときは誠実にする。夷狄のもとに行ったとしても、(これらを)棄ててはならない。
Ⅽ・「子罕篇」: 子欲居九夷 或曰 陋 如之何 子曰 君子居之 何陋之有
孔子は九夷(がいる地)に住もうとした。ある人が言った。「野鄙なところです。それをどうなされますか」と。
孔子が言った。「君子がそこに住めば、どうして野鄙なことがあろうか」と。
Ⅾ・「衛霊公編」:子張問行 子曰 言忠信 行篤敬 蛮貊之邦矣 ・・・
子張が(われわれの道が世で)行われる方法について尋ねた。孔子が言った。
「言葉が忠実で信用がおけ、行動が真面目で鄭重であれば、野蛮な国々でも行われる。・・・
E・「公冶長篇」:子曰 道不行 乗桴浮于海 従我者其由宇與 子路聞之喜 子曰 由也好勇過我 無所取材
孔子が言った、「(わたしの理想とする)道は行われない。(小さな)桴に乗って海を行こうか。
私について来る者は、さて由であろうか」と。子路はこれを聞いて喜んだ。孔子が言った。
「由は、勇敢さを好むことはわたし以上である。(しかし桴の)材料は調達できないであろう」と。(注1)
問題は、紀元前六世紀の孔子の生きた時代に「夷狄戎蛮」などは東西南北という方角と結びついていたのかということにある。しかし、AからDまで、『論語』には夷狄蛮は存在するが、方角は記されていない。単なる「異文化の人々」「異民族」を示しているだけと言えるようである。『論語』では「戎」は記されていない。また、記されている「夷」が東と、「狄」が北と、「蛮」が南と結びつけられるような記述はないことが確認できる。
本稿でこれから述べることは、夷狄戎蛮が方角と結びつけられるのは司馬遷の『史記』やその影響による後代の『論語』の解説書に原因を求めることができるのではないかということを示すことにある。
一、『史記』の夷狄戎蛮 『史記』の功罪
『史記』の著者、司馬遷には二つの顔がある。
一つは儒教信奉者、孔子礼賛者として夏王朝の実在を信じ、早くも夏王朝の堯・舜の時代に北狄・南蛮・西戎・東夷を登場させ、これらの異民族が夏王朝によって支配統制されていたことを語る(注2)。これが司馬遷の一つめの顔である。
『史記』が執筆された時期は前漢時代である。司馬遷が没するのはBⅭ86年ないし87年である。漢という統一王朝(前漢)ができた後で、その周辺部を東西南北の方向を定めることができるようになったのであろう。数多くの周辺にいた異民族、異文化の人々を統合することで統一王国が出来上がった。いわゆる中華意識もその時点で形成されていったのではないだろうか。それと同時に東夷・北狄・西戎・南蛮という概念が確立していったと考えられる。中華思想の原点は夷狄思想と切っても切れない関係にあるだろう。
多くの『論語』解釈とは反対に、例えば大野峻氏は中華思想の原点は夷狄であると述べる(注3)。つまり、氏は中華と夷狄の両者は相関的なもの、相補的な概念であると考えていると言えよう。ということは反対に、明確な「夷狄」意識が生まれ、それらが方角と結びつくという観念は中華思想の誕生があるからと言えるであろう。
これに対して、司馬遷にはもう一つの顔がある。先入観なしに『史記』をよく見ると、夏・殷・周王朝の拠点地域(山東半島から後の洛陽、さらに長安周辺までか)から見て、東北方面に山戎、犬戎がいる。したがって戎は西を意味していない。
また、「夷」の字を持つ鳥夷、島夷は山西省(陝西省の東)にいた。東どころかむしろ西方に「夷」が存在している。これらの「夷」は、当然のことながら、山東半島から東方にある海に出ていってはいない。あくまで中国大陸内部の勢力であった(注4)。これが司馬遷の二つめの顔である。
さらに『史記』では、王都を中心に同心円状に距離によって支配地域の名称が定められている。王城が中心になる。そこから外に向かって甸服・侯服・綏服・要服、そして最も遠くにあるのが荒服(=蛮地・遊牧する夷狄の所在地)と呼ばれている(注5)。どの方角であれ、夷狄の存在する所が荒服である。「夷狄」は決し て方角と結びついてはいない。単なる未開の異民族という以上の意味は持っていない。これが『論語』の「夷狄」概念と一致する。司馬遷のこの二つめの見地が歴史の真実に近いといえるだろう。
反対に、『論語』の「夷狄」などが東・北と結合されたのは『史記』の第一の顔と同様に、前漢の時代状況が投影しているのではないであろうか。
そして、司馬遷の第一の顔と同様のことが『礼記』王制篇についても言える。『礼記』王制篇は前漢の文帝(在位はBC180~157)の時代に書かれたと言われている。だから『史記』と同様に、『礼記』王制篇は前漢の時代状況に基づき執筆された可能性がある。『礼記』王制篇第五 には次のように書かれている。
東方曰夷 被髪文身 有不火食者矣
南方曰蛮 題香趾 有不火食者矣
西法曰戎 被髪衣皮 有不粒食者矣
北方曰狄 衣羽毛穴居 有不粒食者矣
これらに見られる前漢時代の状況が、『論語』の夷狄などの解釈にも影響しているのではないだろうか。
二、『論語』それ自体とその解釈の乖離
幾つかの『論語』の訳本を参考にさせてもらい助かるのだが、他面でそれらの訳や解説によって先入観も植え付けられているのではないだろうか。
(1)代表的な『論語』訳・解説書の問題点
次の『論語』を読んだ。
・吉川幸次郎『 『論語』角川ソフィア文庫
・金谷治 『論語』岩波文庫
・久米旺生 『論語』徳間書店
・平岡武夫 全釈漢文大系『論語』集英社
・吉田賢抗 新釈漢文大系『論語』明治書院
A「八佾」、B「子路」の「夷狄」についての説明や注釈である。
・金谷治氏の注釋。「夷狄—中国周辺の未開民族。東夷・西戎・南蛮・北狄と分けることもある。」
・渡邉義浩氏の訳注。「夷狄は、異民族。東夷・北狄・西戎・南蛮」
・平岡武夫氏はその通釈で次のように記す。【夷狄】天下的世界にいまだ入らず、その外辺にある国々。東夷・南蛮・西戎・北狄。
・吉田賢抗氏は次のように言う。夷狄は、東夷北狄といい、四方のえびすのこと。周辺の未開民族を呼ぶ名である。東夷・南蛮・北狄・西戎といって、四方の未開尾民を四夷と称した。
A・Bの「夷狄」の「夷」が東方に結びつけられれば、Ⅽ「子罕篇」の「九夷」も当然のことながら東方を意味することになる。
この解釈の仕方をより純粋に表現する解釈がある。
・久米旺生氏は、「八佾」「子路」の夷狄と「公冶長」の乗桴浮于海、および「子罕」の「九夷」とが関連すると考える。ここから、「子罕篇」の解説で次のようにこれらの四篇を統合する。
「子罕」の九夷とは孔子が、「筏にでも乗っ
て海に出ようか」と言ったのと同じ心境の
表れである。九夷は夷、すなわち東方異
民族の総称と述べつつ、「八佾」と「子路」の
「夷狄」を参照するように示唆している。」。
・吉川幸次郎氏は、「子罕」の九夷についての解釈として、やはり「東方の異民族」であり、「桴に乗りて海に浮かばん」と同じ思念だと述べている。
その他の『論語』解釈も大同小異である。これらは司馬遷の第一の顔に同調していると言ってもよさそうである。そしてほぼすべての解説で、夷の具体例の一つには「倭人」が念頭に置かれている。
再度繰り返すが、『論語』それ自体には「夷」だけでなく「狄」「蛮」もその方角は示されていなかった。
九夷が東方と結びつくとすれば、たしかにそれは公冶長篇にある「乗桴浮于海」にあるだろうか。中国から見れば海は東にある。
しかしそれは無理な結びつけだ。『論語』は紀元前五~六世紀の時代、日本の縄文時代に当たる。列島の人間が一つの政治勢力として中国に知られている可能性は小さい、いや「国」そのものが無いであろう。国やその支配者の王が存在していないどころか、「クニ」さえできていなかったと言えるだろう。
この「乗桴浮于海」は孔子の希望、空想の産物と考えるのが妥当ではないだろうか。
(2)「九夷」の「九」について
「九夷」の「九」を「九個、九種」とする解釈が一般的である。邢昺『論語注疎』は「九種」の東夷を数える。玄菟、楽浪、高麗、満飾・鳧臾・索家・東屠・倭人・天鄙。また、『後漢書』東夷伝にも九種が載る。
しかし、司馬遷は『史記』で数多くの「九」に触れている(注6)。
九山・九江・九川・九河・九沢・九族・九徳など。これらの「九」は数多くの、幾つもの、ということであり、ぴったり「九つ」あることを意味するわけではない。『史記』では九つの名前が数え上げられることもない。もとより中国の山や川の数が九つであるはずもないないであろう。
また、『書経』「旅獒篇」からの例である。「九仞(かん)の功を一簣(き)に虧(か)く=
土を高く積み上げていきあと少しで完成というときに、あと一籠の土が足りないために未完成で終わった。」
この場合の「九」は明らかに「すごく高く積み上げる」、「大いに」という意味であろう。
「九夷」だからといって「九つ」数える必要はない。
・吉田賢抗氏は「九夷」は東方とする解釈を示している。しかし氏は述べる(注7)。「九」については「九つの」ではなく、「いろいろの」種族と指摘している。この考え方は大事であろう。
(3)『司馬遷の第一の顔への批判
司馬遷の第二の顔に対応する『論語』解釈は管見ながら、見られなかった。
しかし、『論語』の訳書・解説書というわけではないが、冨谷至氏は『漢書』地理志の倭人の記事に疑問を投げかけて、通常の『論語』解釈に異議を唱えている。よく知られている「楽浪海中有倭人 分為百余国 以歳時 来献見云」の前にある次の一文に注目している。
「東夷天性従順 異於三方之外 故孔子悼道不行 設浮於海 欲居九夷 有以也夫
東夷は天性が従順。三方の外に異なる。故に孔子は道の行われないのを悼んで、浮を海に設けて、九夷に居らんと欲す、以ある也夫」
この『漢書』地理志こそまさしく司馬遷の第一の顔に影響されての記述ではなかったか。「無関係の」『論語』のC「子罕篇」の子欲居九夷とE「公冶長篇」の乗桴浮于海二つの文をつなぎ合わせていると冨谷氏は指摘する。つなぎ合わせる手法についての冨谷氏の言葉である。
「海」「九夷」が「海中」「東夷」に関係し、孔
子と東方世界を結びつける鍵詞(キーワ
ード)となっている。(注8)。
先の『論語』解釈者の誤認の根源を見事についているといえるであろう。
最後に臺
紀元前六~五世紀の孔子の時代に、仮に海の彼方の列島にたどり着いたとしても、そこは縄文時代の日本。「国」どころか「クニ」も存在しないし、中国に朝貢する王も存在しない。もとより倭人グループ、倭国、倭奴国も、また邪馬壹国、邪馬泰国、邪馬台国も存在していなかったであろう。
『史記』の持つ二つの顔は、『論語』解釈に混乱をもたらしただけでなく、『漢書』地理志にも負の影響をもたらした可能性がある。そのように見ると、結果的には『史記』、『漢書』地理志という二つの権威ある史書が『論語』解釈とわれわれの歴史観に否定的な影響を与えていたのではないかと考えざるを得ない。
私は、中華思想の確立は中国全土を統一した、早くても秦の始皇帝の時代、遅ければ前漢の時代ではないかと考えている。その前漢の時代意識が司馬遷の歴史観に揺れをもたらし、そのことによって『史記』に二つの顔が現れたのではないだろうか。
(注1)ここでの『論語』の訳は、後に挙げる渡辺義浩 『論語集解』による。
(注2)『史記Ⅰ』ちくま書房、小竹文夫・小竹武夫訳、五帝本紀第一 18頁
(注3)新釈漢文大系 『国語下』季報No.57
(注4)『史記Ⅰ』31頁
(注5)『史記Ⅰ』 36~37頁
(注6)『史記Ⅰ』35~36頁など
(注7)吉田『論語』子罕篇の「九夷」
(注8)『漢倭奴国から日本国へ』r臨川書店 14~15頁