元明紀の「禁書」問題と稗田阿礼の役割
はじめに
私の論考のテーマの一つは、記紀の中からその矛盾点を探ることである。記紀に接続する続日本紀も、特にその書記との整合性を考慮している部分については、懐疑の目を向ける対象になることは後に述べる。このことは当然のことながら、ヤマト朝廷の成立過程について、記紀を信じる立場から展開される定説的理解・教科書的理解にも疑いの目を向けることを意味する。ところで、記紀を疑う立場からは、記紀を資料としては使えないため、圧倒的な資料不足の事態に追い込まれてしまう。そこで、議論をする足場を固める必要から、中国の史書類を第一次資料として信頼することの他にいくつかの仮説を立てていきたい。第二章では、一つ目の仮説として、「外祖父の仮説」を立てた。今回は、記紀の記述に見える綻びをもとに、可能な仮説を提示してみたい。結論を言えば、二つ目に立てられる仮説は「禁書の仮説」である。
ところで、本題に入る前に私の使う「ヤマト朝廷」と「ヤマト王権」という用語について簡単に説明しておきたい。「ヤマト朝廷」は、ヤマトを中心とする王権が、九州を含む広域の範囲に対しても支配を達成し、大宝律令の制定によって支配の安定期に入る701年をもって開始される王権のことである。したがって、それ以降の歴史について語るときには「ヤマト朝廷」を使うことにする。中国の史書、旧・新唐書で「日本国」として描かれる国の王権である。
これに対して、「ヤマト王権」は701年より前のヤマトを拠点とする王権を表すと定義しておきたい。701年より前の時代のヤマトの勢力は漠然としていてとらえどころがない。まず古い時代には、ヤマトの地域における複数の王権が群雄割拠し、並立状況であった時代が長期にわたり続いたと思われる。それがいつの時代に統一された王権として確立するのかは不明確である。新唐書の670年に「日本国の人」が唐を訪れた記事があるので、670年までにはヤマトの王権は列島を代表する、あるいは代表しようという意思を持つ王権に成長していた可能性がある。ヤマト王権は、663年の白村江の敗戦で衰退し弱体化した九州倭国を吸収併合し、広域支配を確立し始めていたのであろう(注)。しかし、それが正確にはいつからなのか、また、どの程度安定した王権であったのかは不分明である。したがって、670年から701年を「過渡期ヤマト朝廷」の時代と呼ぶことも可能である。しかし、唐書は670年以降701年まで日本列島については何も語っていない。この期間には滅びた倭国はもちろん、日本国も遣唐使を送らなかったからである。書記はもとより信頼ができないため、私にとっては、この期間は古代史における空白の30年になっている。したがって私は、「過渡期ヤマト朝廷」については何も語れない。したがって、「過渡期ヤマト朝廷」という分類に実質的な意味は見いだせないことになる。そこで、701年より前の時代は、「ヤマト王権」として一括しておくことにする。統一されていたのか、地域ごとに王権が並立する形で存在していたのかは不明である。
(注)このあたりの詳細は、拙稿「倭国の遣使先と遣使姿勢」、及び「旧唐書と新唐書の間」を参照いただければと思う。
ところで、以上のような私の主張は常識からあまりにも逸脱しているとの批判が起こることも承知している。670年から701年の間の空白期間は、日本書紀においては最も有名な天皇たちの三人が並んでいる時代である。「天智天皇」、「天武天皇」、「持統天皇」の存在や、その時代の「壬申の乱」などの出来事を否定するのかと指弾されることであろう。
そうなのである。残念なことに私はこれらの天皇たちの存在も、その事績も疑っているのである。そのことへの反批判は、私のこの論考:『日本古代史の基礎――記紀から疑う』の全体で述べることなので、ここで直接に触れることは避けたいと思う。
第1節 稗田阿礼、太安万侶の役回りへの疑問
ここから本題に入りたい。記紀への疑いの対象は数多くある。これから述べる私の記紀への懐疑は、古事記序の古事記作成にまつわる事柄についてである。
第1項 阿礼は古伝承の語り部ではない
ここで取り上げる問題は、古事記の序に登場する稗田阿礼の役割についてである。あの有名な稗田阿礼が登場する意味が、私の見る限り古事記の序で語られている意味では、全く存在しないのである。あるいは極めて不可思議な役回りに見えるのである。古事記によると、稗田阿礼は聡明で記憶力に秀でていたと書かれている。ところが、稗田阿礼は自分が覚えていた古い出来事や伝承などを、記憶力に頼って語ったわけではない。古い伝承を伝える、いわゆる「語り部」のような役割をしたわけではないのである。一般にはそう考えられていると思われるが、それは大きな誤解と言える。古事記序をよく見るとそれとは事情は全く違う。
まず天武天皇の時代に古事記執筆が発案されたとされている。天武天皇が実在したのか否か、実在したとして古事記の編纂を指示したのか、またそれはどの時代のことか、それらは古事記だけに書かれていることなので確証がない。その天武天皇の詔である。
諸家に伝わっている帝紀および本辞には、真実と違い、あるいは虚偽を加えたものがはなはだ多いとのことである。(中略)そもそも帝紀と本辞は、国家組織の原理を示すものであり、天皇政治の基本となるものである。それ故、正しい帝紀を撰んで記し、旧辞をよく検討して、偽りを削除し、正しいものを定めて、後世に伝えようと思う。【引用1】
『古事記』(上)全釈注 次田真幸訳 講談社学術文庫 p.25
ここに出てくる「本辞」は後にある「旧辞」と同じものである。
私の論考では引用箇所を除き、両者とも同じ意味で区別なく使ってい
る。
そこに稗田阿礼が登場し、次のように紹介される。
氏(うじ)は稗田、名は阿礼、歳は二十八歳になる舎人がお側に仕えていた。この人は生まれつき聡明で、一目見ただけで口に出して音読することができ、一度耳に聞いたことは記憶して忘れなかった。そこで天皇は親しく阿礼に仰せられて、皇帝の日継と先代の旧辞を繰り返し誦み習わせられた。【引用2】
『古事記』(上) P.26
その後、天武天皇が亡くなるなどで、しばらくこの作業は中断するとされている。
さて、古事記編纂の作業が元明天皇の和銅四年、西暦711年に再開する。天武天皇が実在したとすると、亡くなるのが686年とされているので、先の詔は686年以前のものということになる。天武天皇の詔が発令されてから25年以上が経つ。阿礼も53歳を越えている。そしてこの25年以上の間、したがって元明天皇の先代の文武天皇の治世まではヤマト王権・ヤマト朝廷は帝紀も旧辞も備えないままの状態で放置されていたのであろう。不思議極まりない事態である。帝紀・旧辞に対して無頓着な王権だったと自ら語っているようなものである。必ず各王権の終焉後に史書を作成する中国とはいかに異なっていたことか。中国との交流のなさを露呈しているのであろうか。
それはさておき、元明天皇によって詔が出される。このときは、稗田阿礼に加え、太安万侶も招聘される。
さて天皇陛下(元明天皇)は、旧辞に誤りや間違いのあるのを惜しまれた。帝紀の誤り乱れているのを正そうとして、和銅四年九月十八日に、臣安万侶に詔を下して、稗田阿礼が天武天皇の勅命によって誦み習った旧辞を書き記し、書物として献上せよと仰せられたので、謹んで仰せに従って事こまやかに採録いたしました。【引用3】 『古事記』(上) P.31
まず、最初に上の【引用2】にあった「誦む」、「誦み習わす」の意味を確認しておこう。現代においては、辞書的にみると、「読む」という意味をもつ。歌や詩などを「節をつけて読む」、「吟誦する」という意味もある。「そらんじる」、「暗誦する」という意味もある。また、数を数えるという意味もあるが、ここでは当たらない。往時には、「誦」は歌を「詠む」の詠むの意味も兼ねていたのだろうか。しかしその場合には、新たに歌の文言を創り出すとか、あるいは既存の歌を歌うように声をあげるという意味になり、これも無理な解釈であろう。「誦む」は「読む」であっただろう。
ということは、【引用2】によると「皇帝の日継と先代の旧辞を繰り返し誦み習わせられた」のであるから、天武天皇の時代には、諸家の帝紀や旧辞は存在しており、阿礼はそれをまずは「読ん」だのであり「誦み習う」のであるから「読んで暗誦・記憶」したでろう。しかしこれは奇妙なことになる。【引用1】によると、「諸家に伝わっている帝紀および本辞には、真実と違い、あるいは虚偽を加えたものがはなはだ多い」と言われているのであるから、天武天皇の時代に存在した帝紀・旧辞の原本は誤りを持っていたということである。したがって、阿礼は誤った帝紀・旧辞を「読んで覚える」意味は全くなくなる。また、原本が存在するのであれば、阿礼の記憶に頼らずに、優れた官吏が自分で、目の前にある帝紀・旧辞を読み、誤りを正し、編集し直せば済むはずなのである。時が移り変わり、天武天皇が亡くなるなどしたとしても、原本を保管しておけば済む話であっただろう。これでは、記憶力の優れた稗田阿礼の存在する理由はなくなってしまう。ここから分かることは、先にも述べたように、阿礼は古来からの伝承を伝える「語り部」であったわけではないということを意味する。したがって阿礼の役割は有意味なものではないように思われるが、何か他の役割でもあったであろうか。
さらに不自然なことがある。元明時代の【引用3】では、安万侶が「稗田阿礼が天武天皇の勅命によって誦み習った旧辞を書き記し」の場面は、阿礼が天武天皇の時代に読み「暗記」していたものを安万侶に声に出して伝えたというように解釈できる。ということは、元明天皇の時代には原本の誤った帝紀・旧辞は存在していないことを意味するのであろうか。原本はどこに行ったのであろう。さらに、その場合には、阿礼が25年以上も前に記憶にとどめていたもの、天武天皇の時代に「誦み習った」ものを思い出して安万侶に語ったと解釈されうる。阿礼の記憶力が必要で、役に立つとすればこのような場面であろうか。しかしこれは不自然極まりない。25年以上も前に読み覚えた様々な事象、つまり神代から始まり天皇の系列、皇后たち、各天皇の諸事績、皇子・皇女たちの記録、諸豪族たちの系列とそれぞれの事績、百済・新羅などとの外交関係、熊襲・蝦夷との戦いの記録など、またそれらの年代。それらをすべて誤りなく記憶にとどめる、そのように記憶力に優れた人間が存在するということは不可能であろう。コンピューターのような記憶容量である。あるいは、それこそ神話の奇跡的な出来事のレベルである。そのように解釈するほかない。私のような凡人の想像の範囲を超えている。まさか元明の時代に神話世界を復活させ、稗田阿礼という超人に活躍の場を与えたわけでもなかろう。
しかしむしろ、天武時代には存在した「原本」の「帝紀」「旧辞」が元明時代にも存在していた、そしてそれらを阿礼が音読し安万侶に聞かせる。このほうが余程、自然であるが、古事記ではそうなってはいなかった。古事記序はなぜ稗田阿礼を登場させ、阿礼の記憶力に頼ったのか。ここでの謎は深く大きい。そして、稗田阿礼が「読んだ」オリジナルの原本である帝紀・旧辞は、その後どこに行ってしまったのであろうか。おそらく古代史に関心を持つ人々は口をそろえて言うことであろう。「その失われた帝紀と旧辞をこそ、ぜひとも見てみたかった」、と。私もそれらを見たかった。それこそ「真実の」、日本における「最古の文書」、「最古の伝承」、「最古の歌謡」、「最古の歴史書」に属するものであったはずだからである。いずれにせよ、ここからも「古事記が日本で書かれた最初の文字資料では無かった」ということも読み取れる。
第2項 太安万侶の役回り
安万侶は古事記の編纂は行っていない
さらにここまで見てきたように、どんな形であろうとも、阿礼が安万侶の前で読んだとされる帝紀、旧辞は当然のことながら、「誤りや間違いのある」ものであった。したがって、誰かがそれを正しいものに書き換えなければならない。その役割を果たしたのが太安万侶であったと言われている。安万侶は、「稗田阿礼が天武天皇の勅命によって誦み習った旧辞を書き記し、書物として献上せよと仰せられたので、謹んで仰せに従って事こまやかに採録いたしました」【引用3】と述べているが、「書き記す」、「事こまやかに採録する」というのは、決して阿礼の読んだ過ちを含む内容をそのまま書き記したわけではない。天武天皇の遺志と言われ、そしてそれを引き継いだ元明天皇の意思でもあった「正しい帝紀を撰んで記し、旧辞をよく検討して、偽りを削除し、正しいものを定める」【引用2】。このことが安万侶の任務であったはずである。誤った内容を、正しいものに書き換えることが太安万侶の役目だったということになる。
しかし、この役割は高度な政治的判断を必要とするものである。何を誤りとするのか、何を正しいとするのか。王権の運命を大きく左右する可能性、あるいは王権の基盤を揺るがしかねない危険性をさえ孕んでいる。時の最高権力者の任務でなければならないだろう。この、極めて重大な役回りが、「一介の」正四位の安万侶(死後に従三位が追贈されている)に果たせたとは考えられない。1979年に太安万侶の墓が発見され、安万侶が実在の人物であったと話題になったようである。しかし、そのことによって安万侶が古事記に対して果たしたとされる役割が古事記に書かれた通りであったとか、さらに古事記の内容が真実であったということが証明されたわけではない。
今、安万侶のことを「一介の」と軽んずる言い方をしたが、安万侶に対して無礼な言い方であろうか。上山春平氏は、この時代の重大事、つまり奈良への遷都が元明天皇の詔勅によってなされ、大宝律令の編纂にかかわった筆頭の制作主体は刑部親王であり、日本書紀編纂の責任者は舎人親王であったことを示しつつ、これが表面上のことにすぎなかったとして次のように述べる。
ただ、問題なのは、元明天皇とか、刑部親王とか、舎人親王といった人びと
が、はたしてあのようなモニュメントにふさわしい政治構想の持ち主であったか
どうか、という点です。」 『埋もれた巨像』P.22
ここでは、正四位の安万侶が軽んじられているどころではない。元明天皇も、刑部親王も、舎人親王も軽く見られている。わたしもその通りだと考える。上山氏は古事記と安万侶の関係については触れていなかったが、天皇や皇族の皇子たちでさえ重要な役回りは果たせないと述べるのだから、上山氏にとっても当然、安万侶の古事記に対する位置取りも定まってくるだろう。つまり、安万侶が古事記編纂に対して王権の「名目上の責任者」として何らかのかかわりをもったのかもしれないが、あるいは古事記編纂の実務担当者として何らかのかかわりを持ったかもしれないが、しかし古事記の内容を実質的に決めるためには、政治的決定権、最終判断の権限を有する人物が関与する必要があったはずである。
第3項 「諸家」とは何か―――諸家の仮説
以上の謎の他にも謎は多い。さらにいくつかの謎を追加してそれらを合わせて解明してみたい。まず、帝紀および本辞が「諸家に伝わっている」とあるが、「諸家」とは何を意味するのだろう。王権の下にいる諸皇族であるはずはないし、ましてや各豪族でもない。書皇族・豪族が帝紀を持てるはずもないからだ。帝紀や本辞とは、ある「王権」が一定期間以上は存在し、その歴代の王権やその歴史を文書で記録に残したもの、またその王権によって統治されている地域の国の政治体制、経済活動、民間の伝承や歌などを含む文化活動などを文字で記録したもののはずである。もちろん、帝紀と本辞は唯一無二でなければならないであろう。実際に、古事記序の先の引用箇所でもそのように語られていた。【引用1】の天武天皇の言葉を再び見てみよう。
そもそも帝紀と本辞は、国家組織の原理を示すものであり、天皇政治の基本となるものである。 古事記 P.25
これは明らかに帝紀・旧辞が「諸家にある」ということと矛盾する事態である。帝紀、本辞は律令や正史などに匹敵するものであり、唯一無二の存在でなければならない。
もし、大和の王権が全国的な統治を完了していたのなら、帝紀や本辞が複数あることは本来ならあり得ないことである。「諸家に伝わる」と書いてあるからには、各地に王家が分立し、統一が果たせていない時代の状況が古事記を編纂する直近まであったのではないだろうかと考えざるを得ない。少なくとも強力な権力者が国家統一を果たす直前までは、王権らしきものが複数存在し、各王権がそれぞれの帝紀、本辞を所有していたということであるならば理解できることである。古事記序によって「諸家が帝紀・旧辞を持つ」と語られた時代前後までは王権は統一されていなかったという証になっているのではないだろうか。
ひょっとして、天皇としての天武が架空であり、天武時代と言われる時点で古事記編纂が発案されていないとしたら、古事記編纂の実際の発案は元明天皇の時期であったのかもしれない。というのも、元明天皇の時代までヤマト朝廷は「嘘偽りのない真実の」、そして「唯一の」帝紀・旧辞は作成していなかったのだからである。歴代の天皇の系譜についての疑惑が湧き上がってくる。歴代の天皇の系統図は、古事記編纂の時点に初めて、遅ればせながら「作成された」のではないのか、と。だからこそ、中国の史書類には漢書から旧唐書に至るまで、ヤマトの歴代の天皇の名前が一人も記述されていなかったのである(注)。
(注)初めて天皇の系譜が中国に認識され記録されたのは新唐書においてであり、
ヤマト朝廷の日本国が唐と本格的な外交に乗り出した後のことであった。
すでに述べたように、宋書などに登場する倭の五王は、ヤマトの王ではな
く、九州倭国の王たちであった。
ここで、日本書紀の中で時代を少しさかのぼった時点にも目を転じてみよう。「諸家に伝わる」と述べられた事柄は、日本書紀の「乙巳の変」(645年とされている)という事件の記述とも矛盾することになる。蘇我入鹿が中大兄皇子や中臣鎌足などによって殺害されたあとで、敗北を覚悟した入鹿の父の蘇我蝦夷は自宅に火をつけ自害する。このとき「天皇紀」(「帝紀」)は蝦夷とともに灰になる。天皇紀(帝紀)が実際に存在していたかは疑わしいが。ここに言う天皇紀(帝紀)とは、「蘇我馬子」と「厩戸皇子」(聖徳太子と言われてきたが、高校ではその名前は、もはや使われていない)が編纂に携わったものといわれている。するとその帝紀は「ヤマト王権」にとって唯一無二のものではなかったのだろうか。唯一の王権に複数の帝紀が存在するなどということは、そもそも許されてはならないことである。それゆえ、乙巳の変の時点で蘇我蝦夷とともに焼失した帝紀は唯一無二であったはずである。それでは、帝紀はその後、復元されたのであろうか。そういうたぐいの記事は書紀には書かれていない。焼失した後で復元されていなければ、ヤマト王権はその後、帝紀を保持していないことになる。仮に復元されたとしても、その帝紀が複数存在するなどということも考えられることではない。複数の人物に、各々復元を依頼するなどということはありえない。復元された帝紀も唯一無二でなければならない。それにもかかわらず、「天武天皇」の時代には複数の帝紀が存在するとはどういうことであろうか。明らかな食い違いがある。日本書紀と古事記序との齟齬と言えよう。記紀を信じようにも信じられない問題の一つである。
この点について、人は言うかもしれない。壬申の乱があって、大海皇子(天武天皇)と大友皇子(天智天皇の皇子)の間で対立があったではないか、大友皇子の側に帝紀・旧辞があったかもしれない、と。しかし、まず大友皇子は一つの家にすぎず、複数の「諸家」には当たらない上、帝紀・旧辞を作成するなどの暇もなく滅ぼされてしまったように見受けられる。仮に、大友皇子側が何らかの文書を保有していたとしても、勝者の大海皇子側はすぐさま対処できたであろう。もとより、書記にしか書かれていない壬申の乱である。それに類する抗争があったのかも疑わしい。考古学から文献史学に突きつけられた鋭い指摘もある。壬申の乱のような大事件が起こった痕跡は考古学的には存在しないという説を唱えている考古学者もいる。考古学者の下垣仁志氏は語る。
磐井の「叛乱」が「交戦」をともなったことは否定できないであろう。ところ
が、この実戦の考古学的な痕跡はみいだされていない。それどころか、大化後の
大乱である壬申の乱の明確な戦場遺跡も知られていない。考古学的な痕跡の不在
をもって戦争の存在を疑う姿勢を貫くならば、これら明白な戦争も否定しなけれ
ばならなくなる。
『日本史研究』No.654、2017年2月号「古代国家と戦争論—考古学からの提言–―」
記紀を疑う立場からやや手前勝手で引用させていただき、下垣氏にとっては迷惑な話かもしれないが、日本書紀に記述があるという理由だけで、安易に壬申の乱などを持ち出すことは控えなければいけないと考えている。
以上から、私の推理に基づき、仮説を提示したい。
「諸家」とは、ヤマト朝廷が日本の広範囲を制覇するまで、全国各地方に存在していた「複数の王権」のことであったと思われる。それぞれの国が帝紀やその国ごとの歴史、その文化的伝承を持っていた可能性がある。その記録などを文書に残していたのであろう。当然のことながら、これらの帝紀や旧辞はヤマト中心の歴史や歴史観とは異なっている。ヤマト朝廷の確立しようとする、「悠久の歴史」を持つ「万世一系の天皇制」論にとっては都合が悪い。ヤマト朝廷の実態は701年の大宝律令制定の時期に確立された王権であった。それ以前は混とんとした状況であったのかもしれない。
諸家は九州や関東にあった可能性がある。ヤマトにもヤマトを統一した王権の他に複数の王権があったのかもしれない。その中で、先進文化と悠久の歴史を持つ、特に九州の帝紀と旧辞は、全国の統一を果たしたばかりのヤマト朝廷にとっては危険なものでもあり、同時に魅力的な史資料でもあったのではないか。それこそ垂涎の的であったであろう。前漢のころから数えれば、800年間ほどに渡る中国への遣使や中国からの遣使の資料などもふんだんにあったに違いない。また、九州各地の歴史や民間伝承、歌謡、特に万葉集の元になった古歌群などそが数多くあったに違いない。そこには柿本人麻呂を含む歌なども含まれていただろうか(注)。さらにこのころまでは、九州以外の地域にも王権はあったはずである。ヤマト朝廷はこれらの豊富な文字資料を素材として利用した、そして神代から持統紀までの物語、つまり悠久の時代を万世一系の天皇家が統治するという物語を造作・創作したと考えられる。帝紀は唯一無二でなければならない。「諸家」の帝紀と旧辞は、ヤマト朝廷の帝紀と旧辞に一本化されなければならない。これが、記紀を編纂する直前の出来事であったのではないだろうか。
以上が、「諸家の仮説」である。
(注)万葉歌の多くがヤマト以外で作られた可能性がある。この点は、第九章
「短歌から日本古代史を考える」で述べる。
第4項 阿礼、安万侶の本当の役割
阿礼の仮説
以上から、古事記序に聡明な稗田阿礼が登場した理由について私の考えを述べる。阿礼が必要とされたのは、各地に王権が存在し、ヤマト朝廷によって各地の様々な文書が発見されたことと関係があるのではないだろうか。各地の王権の帝紀・旧辞は各地の言葉、しかもかなり古い言葉も使われていたであろう。奈良時代以前の「上代の言葉」は、ここに属していた。さらに、各地の帝紀・旧辞はいわゆる地方語、方言によって書かれていたことも予想される。しかも、特に旧辞や歌謡などは当該の地域では通じる固有名詞(地名、人名、役職名など)、さらにその地域に独特な言い回しや方言に満ちあふれていたであろう。その地域の日常語で書かれていたはずである。共通語などはない時代である。他地域の言葉を「ヤマト語」に翻訳・通訳する人間が必要であった可能性がある。いわゆる、漢字の読みにおける万葉仮名などの「上代特殊仮名遣い」と言われるものがここに属していたのではないだろうか。
帝紀のほうはどうであろうか。帝紀が漢語、漢文体で書かれていれば、地方ごとの言葉の差異はそれほど大きくなかったかもしれないという意見もあるかもしれない。しかし、ことはそれほど単純ではない。隋・唐以降の中国の漢字音を「漢音」という。南朝以前の中国音を「呉音」という。秦・漢の時代は「呉音」とも異なっていたということも考えなくてはいけないだろう。それらの漢字音の違いも想定しなければならないため、漢文体であるからといって、読み・発音が統一されていたわけではない。日本の古事記、万葉、日本書紀の時代は、中国では「呉音」から「漢音」に変わる過渡期状態であったのである。日本各地での漢語文化も多様性があったであろう。漢文化を受け容れた時代によって、漢語・漢文も大きく異なっていたであろう。この問題は、今後考えていかなければならない私の課題ででもある。
ところで、方言の問題であるが、私が子供のころはまだテレビが浸透していなかった。個人的な経験であるが、母の実家は茨城県であった。そこに住む祖母の語る茨城弁は、「まさしく謎」であった。NHK語と言われる「標準語」で教育を受けた周りの叔母や従兄弟たちに通訳してもらい、初めて祖母との会話が成り立ったという記憶がある。
したがって、稗田阿礼の「聡明さ」が意味するものは、幾つもの地域独特の言葉遣い、「方言」を理解し操ることができるということではなかろうか。阿礼の役割とは、日本各地の古語や「方言」に満ちた帝紀、特に旧辞、歌謡などを解読し、翻訳し、さらに通訳することだったのではなかろうか。先の古事記序の引用箇所にもあった言葉が思い出される。【引用2】の稗田阿礼が紹介されたところで、阿礼は「一目見ただけで口に出して音読できる」とあった。太安万侶を含む他の知識階級の官人たちは「音読」することさえできなかったのである。それを阿礼は「音読し」、理解できたということになる。つまり、畿内に居た「中央」の官人たちには意味を読み取れない言葉や文章が多数あり、稗田阿礼がそれらを解釈し、通訳したという可能性が浮かび上がってくる。もちろん、稗田阿礼が一人でその任務を果たせたかどうかの確証はない。各地の方言を理解する複数の翻訳者、複数の稗田阿礼が存在した可能性もある。それらの「誤り」を発見し、修正する太安万侶の役目を果たす人物も複数いたであろう。
古事記序に書かれた阿礼、安万侶は、ともに一般に思われているような役回りではなかった。これを「阿礼、安万侶の仮説」と名付けてもよいのだが、短縮して「阿礼の仮説」と呼ぶことにする。
禁書の仮説
さらに、ここに言う「諸家の帝紀と旧辞」とは、『続日本紀』の元明紀にある「禁書」を中核とするものではなかったではないだろうかと考えてみたい。「禁書」の実態については続日本紀には記述がないので、その内容については推測してみる他はない。さて、「禁書」についての詔が出されたのが和銅元年、西暦708年であるが、次のように記されている。
山沢に逃げ、禁書をしまい隠して、百日経っても自首しない者は、、、
罰する。 『続日本紀』(上) p.98 講談社学術文庫
「禁書」については続日本紀のこの個所にしか記されていない。そして、禁書の内実は伝えられていないので推測の域を出ないが、単なるヤマトの不満分子・反乱分子や反体制派のものではないであろうと考えてみよう。私はむしろ、「禁書」を各地の王権の帝紀・旧辞に結び付ける誘惑にかられる。禁書という「文書」を保有していたのだから、文字文化の先進地帯のもの、先進文化を体得した人物たちのものであったことは間違いないだろう。708年と言えば、古事記執筆以前である。
さらに、続日本紀に禁書の中身が記述されていないということは、逆に言うと、禁書の内実をヤマト朝廷が語ることができなかったということではないだろうか。つまり、「最近までヤマト以外の各地に王権が存在し、それぞれの王権が帝紀・旧辞を保有していた」などとヤマト朝廷が語れるはずもないからである。そこで、禁書の中身には触れないで、いきなり「禁書をしまい隠して」、「山沢に逃げ」とあったのではないだろうか。
ヤマト朝廷にとっての「禁書」は、それが世人の目に触れることがあってはならないものであったである。「禁書」の詔が出されようと、また出されまいと、あるいは詔が出される以前であろうと、ヤマト王権にとって禁書は禁書なのである。公になっては困る文書群なのである。そういう禁書類は存在していたのである。これらの「禁書類」は間違いなく日本最古の文献に属するものであったと言えよう。ひょっとしたら、記紀以前にあふれんばかりの文字文化が日本で始まっていたとは言えないだろうか。
ところで、禁書とされる文書を持つ者たちが山沢に逃げたのはいつのことであろうか。708年に詔が出されているのだから、それ以前にすでにヤマト朝廷による禁書の捜索が始まっていたことを暗示している。禁書の詔が発せられる以前に禁書の捜索は始まっており、発見されたものは押収する。しかるべき禁書が発見できなければ、何者かが持ち出して逃げ、どこかに隠し持っていることになる。そこで、禁書の詔が出される。唐突に「山沢に逃げ」とあるのはそのような事態を想定させる。したがって、禁書の捜索が始まったのは708年に先立つどこかの時点であろう。唐書によると日本国(ヤマト朝廷)が胎動を始めたのが670年頃であるので、禁書の押収は早ければ、670年にすでに開始されていたのかもしれない。あるいは708年に近い当たりなのかもしれない。権力の掌握後には、禁書の捜索と押収はいつの時点からでも行われていた可能性はある。
ただし、670年という早い時期だとすると、禁書を押収してみたものの、諸家の帝紀や旧辞が不都合であることも、また自分たちにとって利用価値があることもさほど自覚されていなかった可能性はある。まだ、古事記・日本書紀の編纂を志してはおらず、ヤマト王権はそれらの活用方法についてまで思いが巡らされていなかったことも考えられるからである。
それでは、捜索の対象となった諸家とはどこの王権であったろうか。和同六年五月二日、713年に風土記編纂と思われる詔が元明天皇によって出され、各地に呼びかけられている。
畿内と七道諸国の郡・郷の名称は、好い字をえらんでつけよ。郡内に産出する
金・銅・彩色(絵具の材料)・植物・鳥獣・魚・虫などのものは、詳しくその種
類を記し、土地が肥えているか、やせているか、山・川・原野の名称のいわれ、
また古老が伝承している旧聞や、異った事がらは、史籍に記載して報告せよ。
続日本紀(上) P.140
その諸地域の王権のうちの幾つかが、おそらく諸家であった可能性がある。というのも、帝紀や旧辞という文字資料が作成できる文化が育っていた地域は、風土記(注)の編纂も容易であっただろうからである。当然のことながら、九州倭国の帝紀、旧辞などもこの中に含まれていたはずである。
(注)風土記は、56の国で書かれたことになっている。実際には執筆されなかったり、執筆が遅れた地域の風土記もあったであろう。この中でほぼ完全な形では『出雲国風土記』、一部欠損がある『播磨国風土記』、『備前国風土記』、『常陸国風土記』、『豊後国風土記』が後代に伝わっている。他の幾つかの風土記は逸文として他の書物に残されているものもある。風土記については、その文字資料としての価値についてはそれぞれ慎重に評価しなければいけないところがある。例えば、各地の風土記という名前に反して、『常陸国風土記』などは中央の官制ではないかと疑わせる記述が多い。史書類に大きな影響力を持ったのが藤原不比等であり、その三男である藤原宇合が国司として常陸の国に派遣されていた時代の文書資料が『常陸国風土記』である。また、後代に記述されたり書き加えられた可能性のあるものもあるだろう。『陸奥風土記』などは相当に後発の風土記で、これも官制の史資料の一つであろう。個々に検討して、史料価値・資料価値を確認しなければならない。この問題については、後日の課題としたい。
禁書を集め始めたのが708年に先立つある時点であったであろう。元明天皇の時代に帝紀・旧辞の「偽り」を正そうと古事記の編纂を始めたのが711年。もちろん、実際の作業開始はもっと早かった可能性がある。そして『古事記』の出来上がったのが712年。時期的にも無理はない。708年ごろから711年までは、禁書の収集とその扱い方などの検討などが行われていたのであろう。そして「禁書」の扱い方についての結論が出された。利用できることは利用し、必要に応じて改変する。全体としてはヤマト朝廷にとっては不都合なものが多いので、古事記編纂、そしてその後に予定されていた日本書紀の編纂が終われば、「諸家の帝紀や本辞」は廃棄する。
そして帝紀、本辞、つまり「禁書」を廃棄する口実の一つが、これもまた稗田阿礼だったのではなかろうか。
正しい記録は古事記に書かれましたよ。今後、日本書紀にも書かれますよ。記
憶力に優れた稗田阿礼が覚えたので最早、諸家の帝紀・旧辞は必要ありません
よ。間違えや偽りが多かったし。それらは、廃棄してしかるべきです、と。
以上、元明紀の「禁書」の中核をなしていたのは、九州倭国など各地の王権が文書として記録していたものの総体ではなかろうか。
これが「禁書の仮説」である。
私は、古事記と日本書紀の編纂の責任者は同一人物であったと考えている。古事記は日本書紀のエチュード(練習)ではなかったか。歴代の天皇名が同じで、順序も同じでということがそのことを示している。もちろん、古事記と日本書紀の違いはいくつもある。古事記にはない「推古紀」以後から「持統紀」という彼らにとっての近現代史を日本書紀に書き込むことなどもそうである。その中で重要な違いのもう一つは、古事記には中国との国交関係が一切ないのに対して、日本書紀には幾つかの中国との国交史が記録されていることにある。神功皇后紀、推古紀。舒明紀、孝徳紀、斉明紀、天智紀などに中国との国交記事が見られる。
この中で、時代的に早い時期に設定されている神功皇后紀を除けば、日本書紀がカバーすべき推古紀以降には、それ以前と比べて不自然なほど濃密に、中国との国交記事が記述されている。私は、712年の古事記編纂から720年の日本書紀編纂の間に8年ほどの時間差があるが、この期間は中国との国交関係、遣使関係をどう描写するのかに費やされた時間などを大きな要素として含んでいたのではないかと考えている。日本国が姿を現す以前に中国の王権と交流してきたのは、第一章「倭国の遣使先と遣使の姿勢」に述べたように、九州倭国だけであった。したがって、8年間という時間には、670年以前の九州の帝紀や旧辞の中に見つかった中国との国交史をどのようにして取り込むか、ヤマト朝廷は腐心したことが推測できる。
ところで、日本書紀には、その他、「呉(くれ)」との国交関係についての記事が、応仁紀(37年2月、41年2月)、仁徳紀(58年10月)、雄略紀(8年2月、10年
9月)などにも見られる。しかし、相手国が中国一般を表す「呉」では検証のしようもないので割愛した。史料価値があるとは考えられない。いずれにしても、それらも含めて日本書紀におけるこれらの記述からは、中国との国交記事を取り急ぎ追加した感が否めない。
以上のように見てくると、古事記序に書かれていたことは、日本各地の貴重な歴史や文化、伝統の記録が、優秀なヤマト朝廷の官人らによって解読され、役に立つ部分は記紀に採用されて利用され、その後、廃棄される。近畿天皇家の万世一系説にとって都合の悪い原本は廃棄される、その場面の話ではないだろうか。つまり、古事記序に記述されている古事記編纂の計画は、日本各地の貴重な真実の歴史が永遠に失われる直前の場面、いわばその「犯行」計画の描写だったのではあるまいか。稗田阿礼が実在の人物であったかどうか、一人であったかどうかは大きな問題ではない。男性ではなく女性であったという説もあるが、性別も大した問題ではない。実在していたとしても彼、あるいは彼女の名で仕事をさせたのは背後にいた権力者であった。太安万侶の役割も表面上のものであった。元明天皇も表向きの権威に過ぎなかったであろう。この時点での最高権力者は藤原不比等である。彼がその背後にいてタクトを振るっていたのであろう。
第3節 「日本最古の文字文書」という重み
古事記序における「諸家に伝わる帝紀と本辞」と続日本紀の「禁書」の詔は、古事記、日本書紀が編纂される以前に複数の文字文書、歴史文書が存在していたこと、そしてそれらに対するヤマト朝廷の処断の仕方などを、ヤマト王権とヤマト朝廷が自ら図らずも表明したことになろう。また、古事記執筆が712年、それとほぼ同時期に「風土記」を各地に提出するように要請できることからみて、日本列島各地ではすでに文字文化がそれなりに発達していて、すでに様々な文字資料が存在していたのではないかということを推測させる。文字文化を持たない地域に風土記を書くことなど要請することはできるはずもない。中央の官人が乗り込んでいって自ら書くとでもいうのであろうか。それでは風土記の内容や推して知るべし、ということになる。
だから、「禁書」の詔とはそのような各地の文字資料の抹殺行為だったのではなかろうか。そしてその後、言うまでもなく日本最古の文字文書類、歴史文書の一例である「諸家の帝紀や本辞」が日の目を見ることはなかった。かくして古事記と日本書紀は日本に残る最初の文字文書という特権的地位を獲得したのである。
このことの意味は非常に重大である。つまり、古事記と日本書紀で記述された内容と比較対照し、検証することができる文書資料が日本には存在しないことになったからである。そのような絶対的に優位な地位、言い換えると絶対的不可侵な地位を記紀の編纂者は手にしたのである。これこそが記紀編纂者、藤原不比等の目論見であった。そういえないであろうか。これにより不比等は極めてクリーンな状況、つまり白紙の状態から歴史を「造作・創作する」自由を手にしたのであった。その際、記紀を書くための資料も諸国にあった王権の帝紀、旧辞を禁書として押収することによって豊富に揃えられた。このような状況こそが、712年の古事記、720年の日本書紀を書く直前の状況であったと思われる。
記紀の編纂者は藤原不比等であったことは、すでに第二章「不比等が確立した外祖父システム」で述べた。しかし不比等は、彼の死後、日本の古代史研究、また考古学研究の在り方を拘束するという意図までは持っていなかったであろう。ところが、日本古代史の研究、考古学の大多数の研究は記紀から出発し、さらに記紀によって検証するのが一般的慣習になってしまった。つまり、日本古代史は何らかの形で記紀に頼らざるを得ないという状況までも生み出してしまったのである。このことは、記紀が単に日本の「最古の文字文書」としてだけではなく、日本の古代史探求の唯一無二、いや「唯二無三」の「最古の歴史文書」にまで格上げされてしまったことになる。「記紀に書いてあることが正しいのは記紀に書いてあるからだ」という循環論法が成り立つ状況まで作り出されてしまったのである。
私も、日本古代史の勉強を開始するにあたっては、記紀と記紀の研究書から読み始めた。日本古代史の研究は、いわば不比等の手のひらでもてあそばれてきたと言わざるを得ない。そこで私は、ソロバンではないが、日本古代史や考古学の「記紀に基づいた」研究は「ご破算で願いましては!」という形で、一度、白紙に戻さなければならないと考えている。
再度言えば、記紀は日本で「残存している最古の文字文書」であるということはできる。しかし、「真実の最古の文字文書」でもないし、ましてや「真実の最古の歴史文書」ということはできない。したがって、日本書紀は正史の範疇に収めることはできないのである。世に、古代日本の正史は「六国史」だと言われている。つまり、日本書紀・続日本紀・日本後記・続日本後記・文徳天皇実録・三代実録を総称したものである。そこから日本書紀を取り除く必要がある。「六国史―日本書紀=五国史」になる。
日本古代の正史は続日本紀から始まる「五国史」と呼ばなければいけなくなるであろう。そこで、続日本紀より前の日本の歴史の、文書による第一次資料としては中国の史書類になってしまった。このことにより、私たちは日本の古代史研究を行っているにも関わらず、中国の史書に頼らざるを得なくなってしまうという悲劇的な条件が突きつけられてしまったのである。
ところで、ここで追加して述べなくてはいけないことがある。それは、続日本紀以降の「五国史」のすべてを信頼してよいというわけではないということである。日本書紀に続く続日本紀は特に気をつけなければいけない。続日本紀の守備範囲は文武天皇以降である。続日本紀に書かれたことのなかで、文武天皇紀より前の過去の記述もあるが、持統天皇や天武天皇、天智天皇についての記述には、懐疑の目を向ける必要があると考えられる。続日本紀は古事記や日本書紀に書かれたことと齟齬が無いように操作されているという可能性があるからだ。ヤマト朝廷確立を正当化することが記紀であるが、その記紀が疑惑を持たれてしまうようなことが続日本紀に書かれていたとすれば、ヤマト朝廷の正当性と存立基盤が崩されかねないからである。記紀は、ヤマト朝廷にとっての生命線なのであった。したがって、続日本紀は記紀との論旨の一貫性は守られなければならないのである。
第4節 「万世一系」とは
藤原不比等らによる天皇家の万世一系の歴史は、当然のことながら、過去に向かって描かれていく。記紀は天上の神、アマテラスから彼女と血縁関係を持つ皇族の歴史を記述していく。紀元前660年に初代の天皇である神武天皇が登場する。天皇家の血脈は、途中で途切れそうな「危機」も見せながら、その危機を乗り越えて持統紀までを描き上げられた。そして不比等は同時に、自らの氏族である中臣氏、藤原氏が天皇家に対して果たしてきた役割をも忍び込ませることにも成功した。中臣氏、藤原氏の過去に向かったもう一つの「万世一系」をも記述していた。天上の神、アメノコヤネの尊が中臣氏の祖として現れ、中臣鎌足が天智天皇によって藤原姓を賜ることで中臣氏、藤原氏の過去に向かっての「万世一系」は完成する。
しかし、彼の「過去に向かった」天皇家と藤原氏の両家の「万世一系」は当然のことながら真実のものではない。そして、ここで重要な視点は、彼の目指す万世一系は、実は「未来に向かった」両家の「万世一系」を準備するものに他ならないことである。過去の天皇家と藤原氏の物語は、未来に向かった「万世一系」を強固にし、盤石にするためのいわば前奏曲に過ぎない、あるいは露払いに過ぎない。不比等の意識はその後の天皇家と藤原氏の永続的な栄華を保証するところにあったと言えるであろう。そして、それは大成功を収めることになったのである。
ところで、このことに関連して、私が以前から抱いていた一つの疑問を提示してみたい。一般には問題にされないで済まされているのだが、「中臣鎌足が天智天皇から藤原姓を賜る」という話はよく考えると奇妙な話ではないだろうか。古事記や日本書紀では中臣氏の地位は確固としたものがある。天上の神、アメノコヤネの尊が中臣氏の祖と言われているくらいだから、中臣姓はとても有難い姓のはずである。アメノコヤネはアマテラスの側近ではなかったのか。これに対して藤原の姓は、鎌足のところで日本書紀に初めて登場するものである。藤原氏が中臣姓をもらうのであれば、こちらのほうが「有難き幸せ」ということになるだろう。中臣鎌足が藤原姓をもらうということは、「天智天皇」に賜ったのだから有難いということを除けば、むしろ、言わば格下げになるのである。この話を逆にみてみると、伝統を持ち格式高いとされている中臣氏との血統関係が作られることによって、藤原氏は格上げされたということになるのである。ここでは、新参者として日本書紀に初登場する藤原氏が王権の中で確固とした地位を獲得し、それに正当性を与えるための巧みな操作ではなかったかと考えられる。もともと、鎌足が藤原不比等と親子関係であったか否かは書記による結び付けなので確証がある話ではない。このストーリーは、不比等が自らの藤原姓を王権内で高位に位置付ける正当性を見つけるための造作であった可能性もある。藤原氏の「未来への万世一系」を願う不比等の造作・創作の一つでのではなかろうか。
まとめ
この論考で私は三つの仮説を提示した。
諸家の仮説:古事記序の言う「諸家」が、九州倭国を含む各地の王権のことであること。統一以前のヤマトの諸家も含まれるであろう。
阿礼の仮説:稗田阿礼は、各地の事情や言葉に通じており、ヤマトの官人のために解釈、通訳を行ったに人物、ないし人物群であること。
禁書の仮説:元明紀の禁書は、多くは各地の王権が残した文字文書であること。
ヤマトの諸家のものもあったであろう。
三つの仮説は一体のものである。これらを合わせ、一括して「禁書の仮説」と呼ぶが、この「禁書の仮説」は私の論考の様々なところで、私の主張の前提として度々、顔を出すであろう。
最後に付け加えておきたい。ヤマト王権、ヤマト朝廷が「禁書」の存在に気が付き、またそれら禁書の入手はどのように行われたのであろうか。ヤマト王権が、白村江後に弱体化した九州倭国を占拠、支配して文書資料類を押収するということが最も考えやすいことである。あるいは、九州倭国の分派が文字資料を持ち、ヤマト王権に服従の意を示す手土産にしたのかもしれない。あるいはまた、九州倭国の一勢力がヤマト地方に移り、一国をなす勢力になっていったが、ヤマトの王権に制圧され、降伏し「禁書」を没収されたのかもしれない。その争いが「壬申の乱」の物語のモデルになったのかもしれない。いずれにしても、様々な可能性があるだろうが、最終的にヤマト朝廷は「禁書」を手にすることが出来たのである。
“元明紀の「禁書」問題と稗田阿礼の役割” に対して3件のコメントがあります。
コメントは受け付けていません。
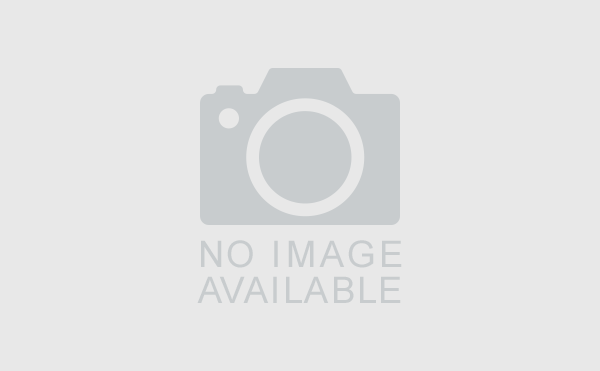
Very interesting points you have remarked, regards for posting.Blog monry
Here to explore discussions, share thoughts, and learn something new along the way.
I like learning from different perspectives and adding to the conversation when possible. Always open to different experiences and meeting like-minded people.
There is my site-https://automisto24.com.ua/
Happy to join conversations, share experiences, and pick up new insights as I go.
I’m interested in understanding different opinions and sharing my input when it’s helpful. Always open to new ideas and building connections.
Here is my website-https://automisto24.com.ua/